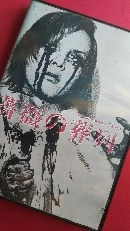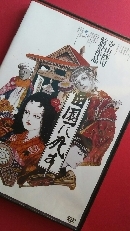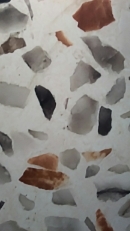やっぱりアングラ演劇が好き!やっぱり実験映画が好き! [映画・演劇雑記]
私・ぼんぼちは、今年の初めまでの2年間、シェイクスピアの台詞のレッスンを受けていた訳ですが、何故、そのレッスンを受けていたかというと、決して「シェイクスピアが好き」だったからではないんですね。
理由は、「演劇・映画に興味があると言いながら、天下のシェイクスピアを殆ど知らないというのは恥ずかしいから、基礎知識くらいは知っておこう」という訳だったんです。ーーーまあ、他にも理由はありましたけどね。
私が演劇でダントツ一番に好きなジャンルは、「アングラ」です。中でも寺山修司氏の作品。
残念ながら年齢的に、寺山演出の寺山舞台を観に行く事は叶わなかったんですが、万有引力とかは鑑賞した事がありますね。
他に、今、現存するアングラ劇団で好きなのは、新宿梁山泊。
あぁ、第七病棟も良かったな。
何故、アングラが一番好きかというと、テントや手造りの木造りの小屋の、土俗的な見世物小屋の様な非現実な空間に、わくわく感を無性に感じてしまうからです。
舞台上もーーー装置も見世物小屋みたいだし、役者さんは、白塗りをしたり、真っ赤な襦袢を羽織って登場したりと、これまた、土俗的で和の匂いに溢れています。
そういう所に惹かれるんですね。
ニ番目に好きな演劇ジャンルは、「不条理」です。
あの、訳の解らなさ に、前のめりになってしまいます。
不条理演劇といえば!のベケットは何作品も観ましたし、ピンターやイヨネスコも愉しみました。
残念なのは、私が不条理の戯曲で最も好きな安部公房氏の「友達」を、まだ舞台では観た事がない事ですね。
どこかの劇団で「友達」を上演するおりは、是非とも足を運びたいと考えています。
三番目に好きな演劇ジャンルは、「社会派」です。
いっとき、坂手洋ニさん作・演出作品は必ず観に出向いていた時期があったのですが、それまで、役者さん達が、きちっと、テーマを運ぶ舟の役割りに収まっていたのに、ある時からポンと、前に出て、自由な事を演り始めたので、私の好みとする社会派ではなくなったため、出向くのをやめました。
さて、映画でダントツ一番に好きなジャンルはーーー
何と言っても「実験映画」です。
長編の実験劇映画にも好きな作品は何作品もありますが、ストーリーのない短編の方が、より好きですね。
松本俊夫先生の「アートマン」、「つぶれかかった右眼のために」、伊藤高志さんの「スペイシー」、ヤン・シュヴァンクマイエルの短編諸作品。
実験劇映画だと、やはり松本俊夫先生の「ドグラ・マグラ」、「薔薇の葬列」、勅使河原宏氏の「砂の女」、「おとし穴」、「他人の顔」、寺山修司氏の「田園に死す」。
ーーー映画を作るなら、つまり、フィルムに焼き付けるなら、このくらい画づらに凝っていただきたい! だって映画って、「映像を観る」のが第一目的なんだから。 それに、テーマのテーゼの仕方も、このくらい安直ではなく、観客を考えさせる哲学を持っていてほしいと思います。
二番目に好きな映画ジャンルは、ビートルズ映画を始祖とする「GS映画」です。
観る側は、「わあ、楽しい!面白い!楽曲にノレる!」と、手放しに愉しんでいい訳ですが、作り手には、複雑なパズルを構成するが如くの、緻密な計算が求められます。
巧いタイミングで違和感なく何曲も楽曲を挿入出来ているか、グループのメンバーは、ファンをがっかりさせない様に、出番が多く大活躍しているか、それでいてストーリーが成立しているか、等々々、、、
私は、その、複雑なパズルが如何に精巧に作られているかを観るのが、好きなんです。
三番目に好きな映画ジャンルは、50S~60Sの、商業の劇映画です。
これは、私がこの時代に大変興味があり、シノプシスや役者さんの演技のみならず、当時のファッションや街並みを、画面を通じて知る事が出来るからです。
ちなみに、好きなスターさんは、海外ではマリリンモンロー、日本では、小沢昭一さん、緑魔子さん、加賀まりこさん です。
以上が、私・ぼんぼちが好きな、演劇・映画のジャンルです。
それにしても、好きなジャンルって変わらないですね。
演劇を知りそめし時から、映画を知りそめし時から、ずーっとこれらのジャンルが、これらの順位で好きです。
演劇・映画に限らず、音楽でも漫画でもタイプの異性でも、変わらないです。
おそらくそれは、私が生まれ持った血液型の様な、連綿と私の内を流れ続けるものが、それらを呼ぶのだと思います。
映画作りに関する些細な雑文 [映画・演劇雑記]
もしも私・ぼんぼちが、映画に関われるとしたら、松本俊夫先生の「アートマン」や伊藤高志さんの「スペイシー」の様な、短尺のスチルアニメーションを作りたいです。
スチルアニメーションがピンと来ないかたはーーー
今記事に付けた3枚の写真が、入れ替わりつつ微妙にアングルを変えながらパパパパパッと映り、間に時折、真っ白な画面がパッ!パッ!と挿入されたものーーーつまり、アート写真作品に時間軸が加えられた表現ジャンル、と解していただくと、解りやすいかと思います。
タイトルは「水面」とし、水面に反射する光や水草の揺れが、半抽象的に訴えかけてくる、美しいアートアニメーションに仕上がると想像します。
私がスチルアニメーションを最初に作りたいと色めき立ったのは、中学1年になろうという時でした。
映画部に入ってそこで作ろう、と、中学受験合格時から、楽しみにしていたのです。
けれど残念な事に、私の入った中学には映画部がなく、仕方なく他の部に入りました。
そして、自分に自由な時間が出来た38才の時ーーー
私は、せっかく潤沢に時間が出来たのだから、先ず映像理論から学ぼうと、イメージフォーラム映像研究所の夏期講習会で、世界実験映画史を学び、あくる年、世界インスタレーション史を受講しました。
どちらも、たくさんの、テキストとされた秀逸な映像作品を観せていただき、講師の講義が詳らかに1作毎に入った、大変に得る所の大きな納得出来る濃密な授業でした。
3年目にはいよいよーーー私は、実験映画を自ら作る、というコースに臨もうと、研究所のパンフレットのそのコースの欄を熟読しました。
すると、「3人ひと組になって1作を作る」とあったので、参加するのをやめました。
私は、自分の映画作りに対する絶対条件として、「スチルアニメーションである事」の他に「たった1人きりで作りあげる事」があったからです。
大好きな映画制作に、自分以外の人間の考えや技術が入って来られるのは、私にとって耐えがたい事なのです。
3人で作らねばならないのなら、何も作らない方を、迷わず選びます。
時はくだりーーー
今現在、スマホとパソコンがあれば、スチルアニメーションは、1人でなんぼでも制作可能な時代になりました。
公開も、YouTubeでなんぼでも出来ます。
けれど今、私はそれをやっていません。
何故かというとーーー
ブログを始めて何年かしてから、アート写真を撮り公開する様になったのですが、時間軸の加わらないアート写真という表現に、まだまだ飽き足らなく、もっともっとたくさんのアート写真作品を生み出したい、という気持ちが強くなったからです。
そうこうしているうちに、私の寿命は尽きるでしょう。
それでもいっこうに構わないと、思っています。
それはそれで、運命の様なものなのでしょうから。
映画やドラマの中の画家はやっているけれど現実の画家はやらない事 [映画・演劇雑記]
長くこのブログを読んでくださっている方はもうすでにご存知の様に、私・ぼんぼち、18歳~27歳まで、画家をやって母親を養っていました。
という事で、今日は、映画やドラマの画家役はしばしばやっているけれど、現実のプロの画家は絶対にやらない事を、挙げたいと思います。
・絵筆を縦に持ち、モチーフに向かって「う〜む」と、しかつめらしい顔をする。
これ、画学生の一年生ですらやりません。
ある程度画業を積んだ者が見ると、まるでコントです。
私は、そういうポーズと表情を役者さんにやらせる監督と もしもお話し出来るチャンスがあったとしたら、「あれは、一体全体、役者さんに何をやらせているつもりなのですか?」と問いたい、謎のポーズと表情です。
・プロの画家なのにデッサンをやっている。
劇中で、プロの画家が、木炭デッサンや鉛筆デッサンを描いている、もしくは、描きあげたデッサンが画室にある、という設定を見ますが、プロの画家は、すでに十二分にデッサン力がついているので、もう一切、デッサンはやりません。
デッサンをやるのは、プロを目指している最中の画学生、もしくは、美術学校を卒業してもまだデッサン力がついていない 出足の遅い志望者かアマチュアだけです。
プロの画家の画室には、デッサンなどという過去に学びきった遺物は、捨てているか、画室の奥深くに放り込んであります。
・専門用語や画材の使い方がめちゃくちゃ。
台詞で「デッサン」「スケッチ」「クロッキー」「エスキース」「タブロー」などの専門用語が間違って使われていたり、画用紙に木炭で描いていたり、鉛筆デッサンを指でこすったり、油絵の具を指で画面に乗せたりと、画学生でも、言わないやらないめちゃくちゃが、しばしば見られます。
・個展の時に、画商がその場にいない。
プロの画家の個展会場で、その場に画商がいなくて、画家と客が話しをしている、という場面をよく見ます。
これも、絶対にありえません。
プロの画家には必ず画商がつき、画家の傍らにピッタリと画商が寄り添っているのが現実です。
何故なら、画商が最も恐れているのは、とっぱらいをされる事なので、画家と客が名刺交換をしたりなどして、とっぱらいに至らない様、客の名刺は全て画商が受け取り、直接の仲にならない様に、常に目を光らせています。
とっぱらいをされると、画家と客が大得をして、画商一人が大損をしてしまう結果となってしまいますから。
・画家が、ギャラリーの搬出入などを、一人でやっている。
これをやるのは、趣味で描いている日曜画家、つまりアマチュアだけです。
プロの画家の個展の場合は、搬出入は業者に任せ、搬入日は、画商は画家の自宅に車で迎えに来て、一緒にギャラリー入りし、届いている作品を「この作品はここがいいですね」と二人で話し合って、展示作品の場所を決めて、業者に指示します。
搬出は簡単なもので、業者がサーッと全ての作品を画商の自宅に送り届け、後日、画商がそれぞれの作品を買った客に配りまわります。
どうでしたか?
みなさんがこれまでに、映画やドラマで観てこられた画家像と、大きく違ったのではないでしょうか?
何故、映画やドラマの中で、こんなトンチンカンな間違いばかりが行われているかというと、脚本家と監督が、きちんと画家に取材をしていないからに相違ありません。
漠然とイメージだけでとか、「以前、○○さんが書いた脚本ではこうだったから、なんとなく真似しておこう」とか「☓☓監督と同じ様に作っとけば、たぶん正解だ」とか、そんなあいまいさで作っているからに相違ありません。
これが、突拍子もない非リアリズムの方向性の作品ならいいんですよ、コントめいたポーズも逆に活きてくる。
けれど、プロの画家の現実をリアルを描くなら、プロの画家にしっかり取材すべきです。
勿論、取材期間は、「はじめまして」から20~30分で、自身の職業のホンネを話してくれる人間などいませんからーーー手品師がタネ明かしをするのと同じですからねーーー少なくとも一年は、密着取材をして、何度も食事や呑みを共にすれば、得られます。
職業によっては、みっちり密着取材をしてから作る映画やドラマも多いのに、何故、画家となると、こうもイメージばかりでトンチンカンな事が連綿と続いているのか、元画家として、首を傾げるばかりです。
映画館で映写装置に不具合が生じ上映が中断した、の巻 [映画・演劇雑記]
先日、渋谷の映画館・ユーロスペースに、「みんなのジャック・ロジエ」特集の中の「メーヌ・オセアン」という作品を観に出向いた。
1980年代半ばのフランス映画である。
観映していると、残り30分と思われる辺りで、画面がすうっと黒くなった。
溶暗の多い作品だったので、私は最初は、「これも溶暗の効果の一つで、ちょっと長めの溶暗なのかな?」と思いつつ、流れるピアノの音楽だけを聴いていたが、いつまでたっても次の画面が出て来ない。
ーーーちょっとおかしいぞ!
するうち、音楽も、プツリと消えた。
そこで完全に、これは劇場側の何かのトラブルだと気がついた。
と、劇場内が明るくなり、スクリーンは真っ白になった。
それから何分後かに、劇場スタッフさんと思われる マイクを通した男性の声が、場内に響いた。
「大変申し訳ありません。只今、映写装置に不具合が生じてしまいまして、急いで復旧作業を行っております。大変申し訳ありませんが、それまでお待ちください。」
私達観客一同は、全員、席に着いたままで、静かに待った。
ーーー20分ほど経った頃だろうか。
今度は女性スタッフさんが、劇場扉を開け、扉の前に立ち、「大変申し訳ありません。映写装置の復旧のメドが立たないので、お客様がた、半券を払い戻すか、次回、無料でご覧になれるチケットとお取り替えしますので、受け付けにお越しください。本日は大変に申し訳ありませんでした。」と仰り、扉から去った。
私達観客は、誰一人文句を発する者もなく、すみやかに座席を立ち、受け付けに向かい、一列に並んだ。
そして、払い戻しかチケットかの希望を伝え、手続きを済ませると、ユーロスペースを出て行った。
受け付けのスタッフさんは、一人一人に「大変申し訳ありませんでした。」と頭を下げていた。
今の時代、映写装置は、ほぼ全てと言っていい率の映画館で、フィルム上映ではなく、DCP(デジタルシネマパッケージ)である。ユーロスペースも例外ではない。
今でもフィルムに拘って、映写技師さんが映写機を回しているのは、私が知る限り、杉並区・阿佐ヶ谷のラピュタ阿佐ヶ谷だけである。
フィルムは、たまに、途中で切れたり止まったりと、不具合が生じてしまうものだが、DCPでも、このような不具合が起ることもあるのだ!この回に観に来たという事は、ある意味、非常に非常に貴重な体験かも知れないな、と思った。
DCPの不具合で、ラストの30分が上映不可能になってしまった事態に対して、スタッフさんがたは、十二分に、埋め合わせになる対応をしてくださったと思う。
ユーロスペース、また観たい作品が見つかったら、出向こうと思った。
ぼんぼちが好きな映画監督・ベスト5 [映画・演劇雑記]
映画好きの向きなら、自身の中で一度は、「好きな映画ベスト○」や「好きな監督ベスト○」を挙げてみたことがおありだろう。
以前、私も当ブログで、「好きな映画」については列挙したので、今日は、「好きな監督ベスト5」を、並べてみたいと思う。
「好きな」だから、客観的には優秀だと評価するけれど、ぼんぼちの好みに合わない監督は入れてなく、又逆に、無骨な面もあるけれど、メンタリティとして大きく共感できる監督は入っている。
では、いってみよう!
第1位 松本俊夫監督
ぼんぼちにとって、松本俊夫監督は、映画の神である。
これほど、「映像」というものに、多視点から多実験を試みた監督は、日本には他にいない。
海外でも、特にフランスで高く評価されている、実験映画監督である。
代表作は、赤外線フィルムで撮影された 怒涛の迫力のスチルアニメーション「アートマン」、
1960年代後期の文化・風俗・ニュースを、2スクリーンに3プロジェクターで映写した「つぶれかかった右眼のために」、
劇映画だと、夢野久作の同名小説を、あえてつじつまの合わないシークエンスにつなげ、観客を訳の解らない世界に陥れる「ドグラ・マグラ」、
ゲイボーイの世界を、オイディプス王を下敷きに構成し、劇中に何箇所も、二丁目を歩くゲイや本物のゲイの出演者へのインタビューなど、ドキュメンタリーを入れ込んだ「薔薇の葬列」などである。
第2位 ヤン・シュヴァンクマイエル監督
アートアニメーション映画では、世界一著名な、チェコのアニメーション作家。
スチル、オブジェクト、クレイ、ピクシレーション、カットアウトと、あらゆる技法のアニメーションで、複雑な事情下にあったチェコへの反体制や、食べる事への異常な執着を表現している。
やはり手作りのアニメーションなので、長編より短編作品の方が圧倒的に充実度・密度が濃く、秀逸である。
私があえて、その秀逸な短編作品群から1作選ぶとしたら、無機物で構成された顔と有機物で構成された顔が戦いを重ね、ラストは、粉々に一体化してゆく「対話の可能性」である。
第3位 勅使河原宏監督
原作脚本・安部公房、音楽・武満徹との三者で創り上げた三部作、「砂の女」「他人の顔」「おとし穴」は、安部氏でこその理論的なシナリオといい、斬新な画といい編集といい、前衛的な効果音といい、名優の名演技といい、非の打ち所のない完璧無欠な映画である。
劇映画というジャンルも、このくらい画に拘ってくれると、美術畑出身の私としては、ストレスを感じずに心地よく鑑賞する事が出来る。
この三部作の中でも、個人的には、非現実な病院内セットや、主役の顔を亡くした男が観た映画という設定の劇中劇が挿入された「他人の顔」に、特に惚れ込まずにはおれない。
第4位 塚本晋也監督
「六月の蛇」で世界のtsukamotoとなる以前の、初期塚本純正作品が好きである。
デビュー作「鉄男」の、鉄化してゆくアニメーションは、目眩を覚えるほどに圧巻である。
又、「東京フィスト」は、私にとっての青春映画で、東京に育った者にしか解らない ビル群こそが己れを包み込んでくれる母体だという観念性には、骨の髄から共感する。
私が、全ての映画の中で、一番泣いた映画作品である。
第5位 寺山修司監督
私は、中学生の時に知った寺山修司氏の存在がなければ、映画にも演劇にも短歌にも俳句にもエッセイにも、ここまで興味を持ち、入り込む事はなかったと言い切れる。
辛い事しかなかった思春期の、心の救済者である。
寺山氏がこの世に存在しなければ、今の私は存在しなかったとすら言える。
それほど己れに影響を及ぼした人物でありながらも、何故5位なのかは、寺山氏の全ての表現ジャンルを観、読み込んでゆくと、氏はやはり「書き言葉」の世界の人だと気がついたからである。中でも、短歌は氏の真骨頂だと思う。
映画作品では、劇映画では「田園に死す」短編実験映画では「ニ頭女」が、良くまとまっていると評する。
とまあ、以上が、ぼんぼちの好きな映画監督ベスト5である。
みなさんは、どんな監督がお好きでおられるだろうか?
以前、私も当ブログで、「好きな映画」については列挙したので、今日は、「好きな監督ベスト5」を、並べてみたいと思う。
「好きな」だから、客観的には優秀だと評価するけれど、ぼんぼちの好みに合わない監督は入れてなく、又逆に、無骨な面もあるけれど、メンタリティとして大きく共感できる監督は入っている。
では、いってみよう!
第1位 松本俊夫監督
ぼんぼちにとって、松本俊夫監督は、映画の神である。
これほど、「映像」というものに、多視点から多実験を試みた監督は、日本には他にいない。
海外でも、特にフランスで高く評価されている、実験映画監督である。
代表作は、赤外線フィルムで撮影された 怒涛の迫力のスチルアニメーション「アートマン」、
1960年代後期の文化・風俗・ニュースを、2スクリーンに3プロジェクターで映写した「つぶれかかった右眼のために」、
劇映画だと、夢野久作の同名小説を、あえてつじつまの合わないシークエンスにつなげ、観客を訳の解らない世界に陥れる「ドグラ・マグラ」、
ゲイボーイの世界を、オイディプス王を下敷きに構成し、劇中に何箇所も、二丁目を歩くゲイや本物のゲイの出演者へのインタビューなど、ドキュメンタリーを入れ込んだ「薔薇の葬列」などである。
第2位 ヤン・シュヴァンクマイエル監督
アートアニメーション映画では、世界一著名な、チェコのアニメーション作家。
スチル、オブジェクト、クレイ、ピクシレーション、カットアウトと、あらゆる技法のアニメーションで、複雑な事情下にあったチェコへの反体制や、食べる事への異常な執着を表現している。
やはり手作りのアニメーションなので、長編より短編作品の方が圧倒的に充実度・密度が濃く、秀逸である。
私があえて、その秀逸な短編作品群から1作選ぶとしたら、無機物で構成された顔と有機物で構成された顔が戦いを重ね、ラストは、粉々に一体化してゆく「対話の可能性」である。
第3位 勅使河原宏監督
原作脚本・安部公房、音楽・武満徹との三者で創り上げた三部作、「砂の女」「他人の顔」「おとし穴」は、安部氏でこその理論的なシナリオといい、斬新な画といい編集といい、前衛的な効果音といい、名優の名演技といい、非の打ち所のない完璧無欠な映画である。
劇映画というジャンルも、このくらい画に拘ってくれると、美術畑出身の私としては、ストレスを感じずに心地よく鑑賞する事が出来る。
この三部作の中でも、個人的には、非現実な病院内セットや、主役の顔を亡くした男が観た映画という設定の劇中劇が挿入された「他人の顔」に、特に惚れ込まずにはおれない。
第4位 塚本晋也監督
「六月の蛇」で世界のtsukamotoとなる以前の、初期塚本純正作品が好きである。
デビュー作「鉄男」の、鉄化してゆくアニメーションは、目眩を覚えるほどに圧巻である。
又、「東京フィスト」は、私にとっての青春映画で、東京に育った者にしか解らない ビル群こそが己れを包み込んでくれる母体だという観念性には、骨の髄から共感する。
私が、全ての映画の中で、一番泣いた映画作品である。
第5位 寺山修司監督
私は、中学生の時に知った寺山修司氏の存在がなければ、映画にも演劇にも短歌にも俳句にもエッセイにも、ここまで興味を持ち、入り込む事はなかったと言い切れる。
辛い事しかなかった思春期の、心の救済者である。
寺山氏がこの世に存在しなければ、今の私は存在しなかったとすら言える。
それほど己れに影響を及ぼした人物でありながらも、何故5位なのかは、寺山氏の全ての表現ジャンルを観、読み込んでゆくと、氏はやはり「書き言葉」の世界の人だと気がついたからである。中でも、短歌は氏の真骨頂だと思う。
映画作品では、劇映画では「田園に死す」短編実験映画では「ニ頭女」が、良くまとまっていると評する。
とまあ、以上が、ぼんぼちの好きな映画監督ベスト5である。
みなさんは、どんな監督がお好きでおられるだろうか?
タグ:好きな映画監督
ぼんぼちが発表会のある所では演技を習いたくない理由 [映画・演劇雑記]
少し前からこのブログを閲覧くださってる方々はご存知の様に、私・ぼんぼち、今、月ニのペースで、演技のレッスンに通っています。
今お習いしている所は、十二分に納得出来、レッスンが開催され続ける限り、通い続けたいと思っています。
理由は先ず、先生が大変に優秀でいらして、「この先生にならついて行きたい!」と、心底思えるからです。
もう一つの理由は、「発表会」なるものがないからです。
これも私にとっては、非常に重要な条件なのです。
何故、私が、発表会がある所では演技をお習いしたくないかというとーーー
20年前、某演劇研究所の日曜クラス(アマチュアのクラス)に在籍していた事がありました。
そこでは半年に一度、研究所内発表会がありました。
ズブの素人ばかりですから、勿論チケット料金は発生せず、観てくださるのは、校長や本科(本格的にプロを目指す人のクラス)の先生や本科生、あとは、日曜クラス生の友人や家族、といった程度でした。
そこで、私が何が嫌だったかというと、発表会そのものが嫌いだった訳ではなく、同じクラスの中に、こんな人が一人いたからですーーー。
ゲネプロの時までは、台本通りの台詞をしゃべっていたのに、本番になると、突然、その人が家で独自に創作してきたらしき台詞を、台本にすると2ページくらい、延々としゃべり始めるのです。
私を含めた他の日曜クラス生は、その人の創作台詞が、いつ始まっていつ終わるのか、皆目解らず、冷や汗タラタラでした。
その人はいつも脇役しかもらえず、いつも主役だった私の4倍くらいの量の長台詞をしゃべらなければ、気が済まない様でした。
創作の長台詞は、ホンの内容には関わらず、必ず、泣き叫ぶものでした。
他の日曜クラスのメンバーが、「はぁ、、、また、やってくれちゃったね」といった呆れ顔を見合わせていると、その人は一人、笑顔で「えへへ〜、台詞、間違えちゃった〜」と、悪びれた様子もなく舌を出すのが常でした。
又、私はその人に、ゲネプロが終わって本番が始まる寸前に、こんな事を言われた事もあります。
「アタシが前を向いて、しゃがんでいる時に、ぼんぼちさんが後ろからそーっと来て、アタシの背中をポンと叩いて『わっ!』って驚かす動きがあるじゃないですか。そこ、そうじゃなくて、アタシのメガネのツルの後ろをガクガクガクってやって、驚かせてもらえませんか?」と。
私は、いきなり先生の演出とは違う、ゲネプロとは別の動きはやりたくなかったので、ゲネプロ通りの、背中を叩いて「わっ!」をやったら、発表会が終わった幕裏で、「ぼんぼちさん!なんで、アタシの言った通りにやらなかったんですかっ!ぼんぼちさんのせいで、アタシが面白く見えなかったじゃないですかっ!!」と、すごい勢いで責められました。
彼女は、自分がやっているこれらの行為が、いけない事だという認識はみぢんもないらしく、「アタシは素直で馬鹿正直だから、人に陥れられるんです」「アタシには何一つとして非がないのに、不当に先生から差別されて、嫌われてるんです」「演劇みたいに集団で何かをやるには、アタシみたいに一人ガマンする人がいないと、成り立たないんですよね」という事を、しょっちゅう吐いてました。
それに対して私が、「、、、えっとねぇ、私が思うにはねぇ、、、」と、原因は彼女自身にあるのだと解らせようとすると、決まって、「あー、はいはいはいはい、ぼんぼちさんのお説教なんて、聞く気ありませんからっ!」と、プイッと横を向いて、話しをシャットアウトしてしまうのでした。
私がそこの研究所の日曜クラスにいたのは三年半の間でしたが、とにかく、発表会でのその人の突然の言動のために、発表会が了ると、いやぁ〜な感情だけが残り、その日の夜は、行きつけのジャズ喫茶で、記憶がなくなるくらいまでしたたか酒をあおらなければ、ストレス解消できませんでした。
これが、私がもう二度と、発表会がある所では演技をお習いしたくない理由です。
無論、どこの発表会のあるクラスにも、こんな人が一人づついるとは限らないとは百も承知ですが、「もしも、もしも、又あんな人がいるとしたら、、、」と、その可能性はゼロではないと思うだけで、私の精神はフリーズしてしまうのです。
もぅ、あんな理不尽な理由でストレスを溜めるのは、こりっごりなので!!
タグ:アマチュア演劇の発表会
シナリオがシーン別に書かれている理由 [映画・演劇雑記]
シナリオを読まれた事のある方は、シナリオというものはシーン別に書かれているのだな、とお気づきになったと思います。
例えばーーー
⑯駅前のカフェ
太郎、スマホを取り出し
太郎「今度の連休なんだけどさあ!」
花子「えっ?」
太郎「こことかー」
花子「、、、、、ごめん」
太郎「え」
花子「、、、仕事なんだ」
太郎「またぁ?」
花子「、、、、、」
太郎「出よっか」
という風に。
シナリオは、この様なシーンをつなぎ合わせて、全体が構成されています。
どうしてシーン別に書くかというとーーー
映画やドラマは、シーン毎にまとめて撮影してゆくからです。
「駅前のカフェ」が、シーン16だけでなく、シーン5にも38にも62にもあったとします。
そうすると、話しの内容の時系列とは関係なしに、「駅前のカフェ」シーンを、まとめて撮影するのです。
特にカフェの様な、他人様に借りる場だと、日時が限定されますし、出逢いの時刻が夕陽の差す時間帯であり、別れの時刻が朝だったとしたら、別れのシーンを先に撮影して、夕刻になったところで、出逢いのシーンを撮影する運びとなります。
又、同じ駅前のカフェの中に、朝時と夕刻のシーンがあるとしても、「⑤夕のカフェ」とか「㊳朝のカフェ」と書いてはいけません。
そうすると、スタッフは、「駅前のカフェ」とは別のカフェを指すのだと判断して、別のカフェの夕刻、別のカフェの朝時を、ロケハンしてしまうからです。
あくまでも、「駅前のカフェ」は「駅前のカフェ」という言葉で統一し、ト書きの冒頭に、「朝」とか「夕陽が差し込む窓辺」と書かなくては、混乱してしまいます。
ちなみに、「駅前のカフェ」の様なシーンのタイトルを「柱」と呼びます。
柱の上に、今回、例で示した様に、シーン順の数字が振られる事もあれば、単に「○駅前のカフェ」と、シーンナンバーは書かれない場合もあります。
そして、シーンはどういった基準で分けるかというとーーー
大きくキャメラをはじめとする撮影機材一式を、移動させるか否かで分けます。
「駅前のカフェの通り」という撮影場所が必要になった場合は、「⑰駅前のカフェの通り」と、別の柱を立てます。
何故なら、カフェの中から表へ、よいしょよいしょと機材を運び出して準備をする訳ですし、今度は、カフェオーナーではなく道路に関しての撮影許可が必要になってくるからです。
したがって、すぐ次のシーンだからといって、同じ日の次の時間帯に撮影するとは限りません。
みなさんも、シナリオを読まれる時、又は、映画やドラマを鑑賞される時、この様な事を頭に思いながらご覧になると、一層、興味深くお楽しみになれるのではないか、とお察しします。
例えばーーー
⑯駅前のカフェ
太郎、スマホを取り出し
太郎「今度の連休なんだけどさあ!」
花子「えっ?」
太郎「こことかー」
花子「、、、、、ごめん」
太郎「え」
花子「、、、仕事なんだ」
太郎「またぁ?」
花子「、、、、、」
太郎「出よっか」
という風に。
シナリオは、この様なシーンをつなぎ合わせて、全体が構成されています。
どうしてシーン別に書くかというとーーー
映画やドラマは、シーン毎にまとめて撮影してゆくからです。
「駅前のカフェ」が、シーン16だけでなく、シーン5にも38にも62にもあったとします。
そうすると、話しの内容の時系列とは関係なしに、「駅前のカフェ」シーンを、まとめて撮影するのです。
特にカフェの様な、他人様に借りる場だと、日時が限定されますし、出逢いの時刻が夕陽の差す時間帯であり、別れの時刻が朝だったとしたら、別れのシーンを先に撮影して、夕刻になったところで、出逢いのシーンを撮影する運びとなります。
又、同じ駅前のカフェの中に、朝時と夕刻のシーンがあるとしても、「⑤夕のカフェ」とか「㊳朝のカフェ」と書いてはいけません。
そうすると、スタッフは、「駅前のカフェ」とは別のカフェを指すのだと判断して、別のカフェの夕刻、別のカフェの朝時を、ロケハンしてしまうからです。
あくまでも、「駅前のカフェ」は「駅前のカフェ」という言葉で統一し、ト書きの冒頭に、「朝」とか「夕陽が差し込む窓辺」と書かなくては、混乱してしまいます。
ちなみに、「駅前のカフェ」の様なシーンのタイトルを「柱」と呼びます。
柱の上に、今回、例で示した様に、シーン順の数字が振られる事もあれば、単に「○駅前のカフェ」と、シーンナンバーは書かれない場合もあります。
そして、シーンはどういった基準で分けるかというとーーー
大きくキャメラをはじめとする撮影機材一式を、移動させるか否かで分けます。
「駅前のカフェの通り」という撮影場所が必要になった場合は、「⑰駅前のカフェの通り」と、別の柱を立てます。
何故なら、カフェの中から表へ、よいしょよいしょと機材を運び出して準備をする訳ですし、今度は、カフェオーナーではなく道路に関しての撮影許可が必要になってくるからです。
したがって、すぐ次のシーンだからといって、同じ日の次の時間帯に撮影するとは限りません。
みなさんも、シナリオを読まれる時、又は、映画やドラマを鑑賞される時、この様な事を頭に思いながらご覧になると、一層、興味深くお楽しみになれるのではないか、とお察しします。
シナリオを習っていた時の話し [映画・演劇雑記]
私は、映画・演劇を様々な観点から勉強し、その方面の造詣を深めたいと思っているので、シナリオ作法の勉強もしてきました。
20年前に 某演劇研究所に入所する少し前、ちょっと通所できる状況になかったので、通信で、某シナリオ研究所で9ヶ月間学び、面談に通える時だけ通い、その間は、週6で1日12時間自主勉強していました。
私が何故、そのシナリオ研究所を選んだかというと、「全てのジャンルをお教えします。 プロを目指す人から趣味として楽しみたい人まで大歓迎!」という謳い文句があったからでした。
私はあくまで アマチュアの趣味として、当時 唯一好きなジャンルだったアート・実験系のシナリオの書き方を知りたくて応募しました。
ところが?!
最初の私のシナリオ作品の先生の添削に、「凝りに凝り過ぎた映像表現で、訳が解らず混乱するばかりです」とありました。
私は、「アート・実験系のシナリオを書いたのだから、映像に凝るのは当然なのになぁ」と理不尽さを感じ、さっそく面談を希望しました。
面談が始まるや、私が「アート・実験系のシナリオを書いたんです」と言うと、先生は、「アートジッケ、、、??? そんなジャンルはありませんっ!!」とヒステリックに否定されました。
どうやら先生は、映画のジャンルに アート・実験系というジャンルがある事を ご存知なかったようでした。
そして先生のお話しを聞いていると、そこの研究所で教えているのは、商業の劇映画だけだという事が判りました。
私は内心、「それならどうして、募集の謳い文句に『全てのジャンルをお教えします』なんてウソを提示するのだろう?!」と 理不尽な気持ちでいっぱいになりました。
けれど、決して安くはない授業料は最初に全額払いだったので、元を取らなければ損!何としても元を取ってやるぞ!と 全く興味のない商業の劇映画のシナリオを書く事にしました。
自分が書きたかったアーティスティックさをゼロにして、ありていの映画のようなシナリオを書いて行ったら、「シナリオというものが解りましたね。 アナタ、是非、城戸賞に応募しなさい!」と強く薦められました。
城戸賞というのは、自分の人生経験を元に起こした商業の劇映画の プロの脚本家の登竜門の賞なのです。
私は、「プロフィールに、『アマチュアの趣味として学びたいです』と書いたのになぁ」と ここでも理不尽な気持ちになりました。
けれどーーー
私はそのシナリオ研究所で学んだ9ヶ月間は、決してムダだったとは思っていません。
それまでどういう観方をすれば良いのかかいもく解らなかった商業の劇映画の観方というものが解ったからです。
具体的に例を挙げるとーーー
私はそれまで「親が死んで悲しんでいる」という展開に、何故、何の説明もなく「親が死ぬと悲しい」という感情が出てくるのかが謎でした。
親が死んで悲しい人もいれば、嬉しい人もいるじゃないか、それは個人個人違うじゃないか、どうしてそこを説明する件りがないのだろう?ーーーと。
それが、先生のシナリオ作法の教え、つまり商業の劇映画では、世の中の多数派の人達の立ち位置に立って、世の中の多数派の人が疑問に思わない事は説明しなくて良く、世の中の少数派の人の感情や行動には説明が必要 という事でした。
私は、「あっ!そういう理屈なのか! 商業の劇映画というのは、多数派大前提で書くもの・書かれているものなのか!」と大きく気づかされました。
それからは、自分で 大衆ウケするシナリオを書く事もスラスラとできるようになりましたし、自分が観客として映画を観る時にも、「あぁ、これは多数派の人の話しだから、私にはその感情は理解はできないけれど、そういうものなのだ」と 理論的に理解ができるようになりました。
又、私が最初に書いて行ったアート・実験系のシナリオが何故、映像が凝り過ぎているためにダメだと言われたかというと、商業の劇映画のシナリオ(先生の仰るにはシナリオというもの)は、日本の端っこに住んでいる漁村のおじいさんが観ても解るように書かなければならないのがお約束 なのだという事も知りました。
よって 以来、私は商業の劇映画を観ても、その中に面白さや魅力を見い出せ 楽しめるようになり、観たい映画作品の数、前のめりに観られた映画作品の数がどっと増え、私の中で、映画の造詣の幅が、ぐぐっと広がりました。
演技のワークショップの審査に通りました!! [映画・演劇雑記]
私・ぼんぼち、先日 応募していた某演技のワークショップ(一回完結のレッスン)の審査に通りました!!
合否結果待ちの間は、夜も眠れないくらいにドキドキで、こんなに緊張したのは、中学受験の合否待ち以来で(私は受験は、中学受験しかしていないので)審査が通った通知を見た瞬間、思わず「やったーーー!!!」と 両手を天に向けてバンザイしてしまいました。
今回のワークショップで教えてくださる講師は、某劇団の団員を経て、その劇団の幹部になられ、舞台や声のお仕事で活躍されている プロ中のプロのかたです。
私はあくまでアマチュアというスタンスではありますが、これまでに、演技の研究所に3年半、朗読の研究所に3年半 在籍していた経験があります。
私の強固な意思として、アマチュアの域を出るつもりは毛頭無いけれど、自己満足サークルの様な場ではなく、プロ中のプロの先生に、正しいメソッドを厳しく指導していただきたい、という気持ちがあります。
今回のワークショップは、私の理想とするキャリアの講師で、又、応募書類記入項目に、プロダクションに所属している人はプロダクション名も書き込む欄があったりと、プロの人達に混じってのレッスンとなります。
この点も、私の望んでいた事です。
私はここ何年か、何処か本格的な演技のワークショップで勉強したい勉強したいと熱望しながらも、私の望むスタンスのワークショップが見つからずに、演技をする事に対して 非常に飢えた状態でした。
今は、砂漠を彷徨った末に湖を前にしたラクダさながらの気持ちです。
今回のワークショップ、テキストは、演劇に興味の無い人でもご存知の「ロミオとジュリエット」です。
私はこれまで、シェイクスピアを勉強する機会が無かったので、シェイクスピアに関して詳らかな知識も無ければ、「ロミオとジュリエット」を黙読した事すらありません。
ですから、前もって、そこを勉強しておかねば!と思っています。
ワークショップ当日が2月28日で、その4、5日前に テキストとなる「ロミオとジュリエット」の部分戯曲が送られてきます。
予習出来る日にちは、僅か4、5日ですから、その間、1日6時間は自主練しておこうと思います。
さあ! これから28日まで忙しくなります!
コーヒーを飲みに行ったり、カラオケに行ったり、外飲みをする時間などありません。
先ずは、ブログ記事の予約投稿を、今月末までまとめてやっておいて、(普段はたいてい3、4記事くらいの予約投稿で更新しています)神保町の古本屋で、シェイクスピアについて書かれた本と、「ロミオとジュリエット」が収録されている1冊を買い、熟読し、そしてテキストが送られてきたら予習に邁進するーーーと。
なお、ブログのコメント返しや、みなさんへのブログ訪問は、独学や予習の休憩時間や、夜 家飲みしながらと、合間を見つけられるので、これまで通りに出来ると思います。
今、私の身体の全細胞が、熱く燃えています!!
私って、ほんとに骨の髄から、演技が好きなんだなあ。
義務教育の科目に「演技」を! [映画・演劇雑記]
私は、三十代後半から四十代前半にかけて、某演劇研究所で演技のレッスンを受けていました。
現代の演技のレッスンというものを受けて、強く思った事があります。
それはーーー
「演技」を義務教育の科目の一つに入れるべきだ。
です。
何故そう思ったかというとーーー
現代の演技の基礎レッスンというのは、発声練習をしたり 台詞を読んだり 柔軟体操をしたり という以前の段階で、人間として生きるに必要な 基本的な事を培う事をやるからです。
具体的な例を挙げるとーーー
一人づつ、他のレッスン生の前に立って、他のレッスン生は、前に立っているレッスン生を取り囲んでじーーーっと見る。
立っているレッスン生は、目を伏せたり 腰が引けたりせずに、堂々と前を向いたまま立っていられるか、を試す。
二人が椅子に座って他愛もない話しをして、後、他のレッスン生に、「この人は、どういう人格・性格に感じられましたか?」「こちらの人は?、、、」と問い、自分が他者からどう見えているか、を知る。
二人で向き合い、先ず、三十センチ離れて呼びかけ合う、次に一メートル離れて呼びかけ合う、その次にはニメートル、その又次には、レッスン室の端と端から呼びかけ合い、距離に相応しい声が出ているか、を確認する。
ーーーなどです。
よく買い物をしていると、会計時に、不機嫌顔で目を伏せたまま、聞き取れない小声でボソボソと、客に伝えなければならない事を発する店員がいます。
接客の基本は、笑顔でお客様の目を見て、お客様に伝わる声の大きさと滑舌で言わなければなりません。
又、客側の立場として、酷く店員さんに失礼な態度を取る人がいます。
以前 友達になりかけていた人は、私には優しい言葉使いと態度なのに、中華料理屋さんでビールを追加注文した時に、私に顔と身体を向けたまま、ビール瓶を持った片手を背中のほうに伸ばして、「ビールーっ!!!」と、怒鳴りつける様な口調で注文していました。
私はその態度が余りにも礼儀に欠けるものだったので、結局、その人と友達になるのを止めてしまいました。
こういった言動は、小中学生の時点で、前述の、コミニュケーション能力を培う学びをしていれば、起こす人は殆どいなくなると思われます。
コミニュケーション能力を培うレッスンが了ったら、「誰か別の人物になってみる」レッスンに入ります。
他者を疑似体験するという事は、他者の感情を理解する事です。
つまり、それには先ず、他者の、目の色や動きや 口調や 身体の動きや 呼吸で、他者が今、どういう感情になっているか、を読み取れなくてはなりません。
人の中には、他者の感情が、ハッキリキッパリ言葉で伝えないと、何一つとして察する事が出来ない人がいます。
相手が大激怒して初めて、「えっ?、、、怒ってたの?」と驚いたり、大号泣して初めて、「そんなに辛かったなんて、ちっとも解らなかった、、、」と ポカンと言ったり。(私の一度目のダンナが、まさにそういう人でした)
これも、他者の感情を読む訓練をやっておけば、こんな大人は出来上がらずに済む訳です。
これらの理由から、「演技のレッスン」は、人間としての基本中の基本の、人間として生きるに必要不可欠の、大切な学びだと思わずにおれないのです。
文部省さん、義務教育の科目に「演技」を、どうか導入して下さい!!