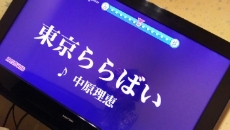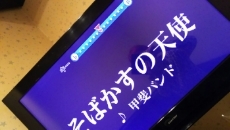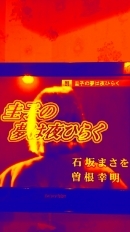ぼんぼちお気に入りクリスマスアルバム [音楽雑記]
私・ぼんぼちは、12月1日になると、衣替えならぬ音楽替えをします。
ふだん聴いている ブルースやブルースロックやブギウギピアノやGSや好きなアイドルから、三枚のお気に入りのクリスマスアルバムに版を替え、25日までの間、それらを毎日 聴き続けるのです。
先ず一枚目はーーー
サッチモをはじめ ライトニンホプキンスやエラフィッツジェラルドといったそうそうたる顔ぶれの、1925年から1971年にかけての、様々なクリスマスブルース&ジャズを編集したもの。
ブルースでクリスマス??と小さく驚かれたかたも少なくないとお察ししますが、お察し通りに、ブルースのクリスマスソングは、あまり、、、というか、まるでハッピー感がなく、ただただブルージーに渋いだけです。 私は大のブルース好きなので、それも又 乙なものだと聴き入りますが。
ジャズのほうは、いかにもクリスマス!めでたいよ!楽しくやろうよ!といった雰囲気が、ジャカジャカ伝わってきます。
又、ラストには、サッチモが、クリスマスにまつわる詩を朗読しているのも、一興です。
二枚目はーーー
シナトラの唄う ジャジーなクリスマスソング集。
シナトラというと、晩年のポピュラーソング「マイウェイ」を思い浮かべるかたが圧倒的に多いのでしょうけれど、私にとってのシナトラは、もっと若かった頃のーーーそう、ミュージカル映画「踊る大紐育」のチップ役なんですね。 ポピュラーシンガーではなく、ジャズシンガーとしてのシナトラ。
このアルバムは、三枚のうちで一番、華やいだ 豊かな 幸せ感に溢れたイメージです。
街のきらびやかなイルミネーションが目に浮かびます。
毎年、三枚の中でどのアルバムを最も多く聴くか、「今年のマイ・ベストワン」がおのずと決まるのですが、今年はこのシナトラのアルバムです。
私が今現在、最高に幸せ感に包まれているからかも知れません。
そして三枚目はーーー
ビングクロスビーのアルバム。
クロスビーらしい ソフトで柔らかな唄い方で、世界中の子供達の知る王道のクリスマスソングから、クロスビーといえば!の「ホワイトクリスマス」も、勿論 収録されています。
私は「クリスマスソングといえば、どの曲を一番最初に思い浮かべますか?」と問われたら、一もニもなく、クロスビーの「ホワイトクリスマス」と答えます。
それくらいこの曲は、私の持つクリスマスのイメージに、パズルがピタリと当てはまるが如く、の一曲です。
聴くたびに、目の前に、温かく灯る古びた暖炉が現れ、その脇には、上品な飾り付けをされたモミの木がきらめきます。
以上三枚が、私にとっての、マイクリスマスアルバムです。
みなさんにとってのクリスマスアルバムは、何かおありでしょうか?
又、クリスマスソングといえばこれ!という一曲もおありでしょうか?
今のカラオケの課題曲ーーー歌詞がいい楽曲を歌いたい [音楽雑記]
ブルースとブルースロックが好きで カラオケでもそればかりを歌ってきた私・ぼんぼち、何年か前からそれ以外のジャンルも歌えるようになりたいと、けっこうたくさんの流行歌を練習してきました。
そして今は、以下の十曲を、素人の趣味の範囲なりに自主練しています。
選んだ基準は、先ず第一に、歌詞がいい事、第二に、その詞とメロディーが一致している事です。
・「硝子坂」(高田みづえ)
「歌謡曲」というジャンルで、これほどまでに文学的・観念的な詞があったのか!と、それまでちょっと軽く認識していた歌謡曲を見直した一曲。
好きな相手の心にたどり着く過程を、ガラスの坂に例えた名曲です。
中でもサビ部分の「♪いじわるなアナタは いつでも坂の上から 手招きだけをくり返す」というフレーズには 舌を巻かずにはおれません。
恋愛をしていると、相手が何の気無しにした言動や 他の理由があってした言動が、えてして「自分に対するいじわる」と感じられてしまうものです。
やはりこのサビ部分を、最も声を張り 切なさを込めて歌いたいと思っています。
・「横須賀ストーリー」(山口百恵)
「♪これっきりこれっきり もぅ これきりですか」というサビが冒頭に持って来られている インパクトのある楽曲。
曲中、何度もくり返し出てくる「♪これっきり、、、」の意味が、ラストのコーラスで明かされます。
一見 単なる横須賀の街の状況説明かと思われる箇所も、実は 主人公の心情を表現しているというところも心憎いです。
最後の最後の「♪これっきり、、、」を、思い切り声を飛ばして 訴えかけるように歌いたいです。
・「横浜いれぶん」(木之内みどり)
蓮っ葉を装ってはいるけれど、実は純な女の子が、今夜こそはアナタについてゆくわ!といった内容の歌。
「いれぶん」は、午後十一時の事で、この歌の現時刻です。
「♪アンタの傷をいやすのは 海鳴りよりも どしゃ降りがいい」というフレーズも実に詩的で、聴く者それぞれの内にイメージをふくらませてくれます。
・「酔っ払っちゃった」(内海美幸)
いかにもスナック歌謡といった 詞とメロディーとアレンジ。
惚れた男に振られた女が、やけっぱちになって呑んだくれている という設定なのですが、今でもその男の事が好きで好きでたまらず、また、振られて悲しくはあるものの そんな自分にナルシスティックに精神面でも酔っている という、決して上品ではない主人公の心情が面白い一曲です。
ですから、暗くならずに、むしろ笑顔を作りながら、これでもか!というくらいにエグく歌うのが相応しいと解釈しています。
・「セクシー・ナイト」(三原順子)
ナイトクラブで一夜限りの恋愛を享しむ 刹那的な女性主人公。
「♪アナタの優しい嘘に 今だけうなづいてみる」と、これが擬似恋愛であると承知の上で、自分からも誘う女心を、ちょっと色っぽく歌いあげてみたいです。
・「君のハートに火をつけて」(あいざき進也)
意中の女の子を狙ってはいるものの まだ踏み出せずに焦る青年の繊細な心を歌った楽曲。
ワンコーラス目の「♪はやくしないと」がツーコーラス目に「♪は〜や〜く〜しないと」となっているところが、時間経過と共に焦りがつのる気持ちが巧みに表現されています。
ロックンロール調歌謡曲で、私は、あいざきさんのシングルカットされた楽曲の中では、これがダントツ一番にお気に入りです。
・「悲しき片想い」(弘田三枝子)
・「子供じゃないの」(弘田三枝子)
・「カッコイイツイスト」(弘田三枝子)
・「私のベイビー」(弘田三枝子)
この四曲は、世代を越えて多くの人に知られているオールディーズスタンダードナンバーの和訳カバーですね。
オールディーズの和訳カバーは誰が最も多く歌っていらっしゃるか調べたところ、あんのじょう弘田三枝子さんだったので、弘田さんのCDを買い、どの音符にどの語が当てはめられているかを 正確に覚えました。
アメリカ製の曲に当てはめながら日本語訳をするのは 並大抵の技術ではないと察するのですが、これらは見事に当てはまっていて、感情を乗せるのにも全く違和感を感じません。
私は特に、「子供じゃないの」と「カッコイイツイスト」の、詞とメロディーが好みです。
以上の十曲が、今、私がカラオケボックスに通って 楽しみながら練習している楽曲です。
同世代の人とカラオケに行き、ブルースとブルースロックばかりを歌うと、必ずと言っていいほどに「ぼんぼちさんが歌った歌、全部知らなかった」と言われてしまうので、そういう点でも、今回の課題の十曲は、私と同世代の人は間違いなく知っている曲ばかりだから、そのような機会にも披露したいと考えています。
カラオケの今年の課題「感情表現にたより過ぎない事」 [音楽雑記]
相も変わらず二日に一度のペースで カラオケを愉しんでいる私・ぼんぼちですが、今年は練習する時に 特にこの事に気をつけて前進しようと目標を立てています。
「感情表現にたより過ぎずに、リズムと音程の正確さを目指す」
私は以前、あくまで趣味という範囲でですが、演技のレッスンを受けていた期間があり、よって 声量と感情表現は得る事が出来ました。
けれど歌唱は、専門的にお習いした事がないので、リズムと音程はてんでなっていません。
なので、ブルースとブルースロックだけはーーー元々 最も好きなジャンルだという理由もあってーーーなんとか形がつくくらいには歌えます。 あくまで所詮は素人のレベルですが。
ブルースとブルースロックというのは、リズムや音程よりも感情を前面に出したほうがサマになるジャンルなんです。
しかし、いつまで経ってもブルースとブルースロックだけでは レパートリーが広がらないし、他のジャンルの楽曲にも「歌ってみたいなぁ」と惹かれるものが幾つもあるので、近年は、他ジャンルにも挑戦する様になってはいたのですが、やはりどうも、歌詞の意味、つまりは感情表現にばかりたよって ごまかしていたので、今年こそは徹底して、感情を控えるべき所はぐっと控えて、リズムと音程の正確さを追究しようと決意した訳です。
そもそも、ポップスやロックやフォークや歌謡曲のほとんどは、そういった歌い方をしないと クサいーーーつまり、クドく 押し付けがましく 一人よがりな、聴いている人を鼻白ませる印象になってしまうのです。
ーーーという事で、今年 先ず、選んだ課題曲は、以下の十一曲です。
「想い出ぼろぼろ」(内藤やす子)
「東京ららばい」(中原理恵)
「恋の季節」(ピンキーとキラーズ)
「お手やわらかに」(夏木マリ)
「プカプカ」(西岡恭蔵)
「ハイウェイのお月様」(RCサクセション)
「漂泊者(アウトロー)」(甲斐バンド)
「そばかすの天使」(甲斐バンド)
「ちんぴら」(甲斐バンド)
「ポップコーンをほおばって」(甲斐バンド)
「感触(タッチ)」(甲斐バンド)
「想い出ぼろぼろ」は、「♪つくろう〜」「♪よそおう〜」の部分は、本曲で最も高音で声を張るべき所で、そこを感情を込め過ぎると、悲痛になり過ぎ 弱くなってしまうので、そうならない様、気をつけようと思っています。
「東京ららばい」は、歌詞に男女のダイヤローグが入るのですが、ここも、カミシモつける様な調子で歌ってしまうと、テムポあるリズムから外れてしまうし クサくなるので、淡々とやり過ごし、その後の「♪ねんねんころり ねころんで〜」で初めて 遊んでる女ぶって誘うように感情をふうっと出そうと 練習しています。
「恋の季節」は、頭から声を張って響かせて歌うタイプの歌なので、声量を使って「♪忘れ〜」と出、サビ後の「♪死ぬまで私を〜」「♪夜明けのコーヒー〜」で、ふっと弱くする事で緩急をつけるのが相応しいと 考えています。
「お手やわらかに」は、歌謡曲の中では、感情をかなり出してあえてクサく歌ったほうが面白いお色気ソングなので、私にとってはそれほどハードルは高くはないのですが、あくまで リズムと音程をないがしろにしない事を忘れずにいようと心しています。
「プカプカ」は、のたりんとしたメロディとプカプカプカという擬音に 楽天的な楽曲だと誤釈されがちですが、「♪おいら明日死ぬそうな」の辺りからこの楽曲の本質が見え、実はこの曲は、断崖絶壁ぎりぎりの位置に生を留めて立っている女性の歌だという事が判ります。
ですから、「♪おいら明日〜」以前の部分は感情を抑えて、いわば映画のラストが判らないが如くに歌おうと努めています。
「ハイウェイのお月様」。 これも私にとっては そうハードルは高くなく、感情を出して歌うほうが合うバラードです。
「♪暗い暗い暗い道に」で、ぐーっと声を張り、「♪迷わせないで」を囁くように歌おうと考えています。
そして最後に甲斐バンドの楽曲。
私は甲斐よしひろさんの刹那的な世界観というのが無性に好きで、、、というのは、ロックでありながらも非常に歌謡曲的な要素の強いーーー別の言い方をすると、どの楽曲もメロディと詞が見事に合っていて、一曲一曲がそれぞれに、単なるメッセージソングを超えた「詩」「ドラマ」に仕立てられているからです。
テムポが早かったり 三連符が多かったりと、私にとっては大変ハードルが高いのですが、好きさ故に、なんとか練習を重ねて歌えるようになりたいと 切に願っている次第です。
中でも、不良少女の投げやりな哀しさ溢れる「そばかすの天使」は、何としてもモノにしたいところです。
以上が、今年、先ず 私が課題に選んだ十一曲です。
勿論、「感情を控える」というのは、「感情を入れない」「感情を考えない」とは違う訳で、詞全体をまるっと飲み込んで 正しく解釈し、その上で、控える所は控え 出しても良い所・出すべき所は出す、という意味です。
まあ、こんな心構えで、丑年な事だし、牛歩ほどにも前進出来れば、、、と目論んでいます。
「感情表現にたより過ぎずに、リズムと音程の正確さを目指す」
私は以前、あくまで趣味という範囲でですが、演技のレッスンを受けていた期間があり、よって 声量と感情表現は得る事が出来ました。
けれど歌唱は、専門的にお習いした事がないので、リズムと音程はてんでなっていません。
なので、ブルースとブルースロックだけはーーー元々 最も好きなジャンルだという理由もあってーーーなんとか形がつくくらいには歌えます。 あくまで所詮は素人のレベルですが。
ブルースとブルースロックというのは、リズムや音程よりも感情を前面に出したほうがサマになるジャンルなんです。
しかし、いつまで経ってもブルースとブルースロックだけでは レパートリーが広がらないし、他のジャンルの楽曲にも「歌ってみたいなぁ」と惹かれるものが幾つもあるので、近年は、他ジャンルにも挑戦する様になってはいたのですが、やはりどうも、歌詞の意味、つまりは感情表現にばかりたよって ごまかしていたので、今年こそは徹底して、感情を控えるべき所はぐっと控えて、リズムと音程の正確さを追究しようと決意した訳です。
そもそも、ポップスやロックやフォークや歌謡曲のほとんどは、そういった歌い方をしないと クサいーーーつまり、クドく 押し付けがましく 一人よがりな、聴いている人を鼻白ませる印象になってしまうのです。
ーーーという事で、今年 先ず、選んだ課題曲は、以下の十一曲です。
「想い出ぼろぼろ」(内藤やす子)
「東京ららばい」(中原理恵)
「恋の季節」(ピンキーとキラーズ)
「お手やわらかに」(夏木マリ)
「プカプカ」(西岡恭蔵)
「ハイウェイのお月様」(RCサクセション)
「漂泊者(アウトロー)」(甲斐バンド)
「そばかすの天使」(甲斐バンド)
「ちんぴら」(甲斐バンド)
「ポップコーンをほおばって」(甲斐バンド)
「感触(タッチ)」(甲斐バンド)
「想い出ぼろぼろ」は、「♪つくろう〜」「♪よそおう〜」の部分は、本曲で最も高音で声を張るべき所で、そこを感情を込め過ぎると、悲痛になり過ぎ 弱くなってしまうので、そうならない様、気をつけようと思っています。
「東京ららばい」は、歌詞に男女のダイヤローグが入るのですが、ここも、カミシモつける様な調子で歌ってしまうと、テムポあるリズムから外れてしまうし クサくなるので、淡々とやり過ごし、その後の「♪ねんねんころり ねころんで〜」で初めて 遊んでる女ぶって誘うように感情をふうっと出そうと 練習しています。
「恋の季節」は、頭から声を張って響かせて歌うタイプの歌なので、声量を使って「♪忘れ〜」と出、サビ後の「♪死ぬまで私を〜」「♪夜明けのコーヒー〜」で、ふっと弱くする事で緩急をつけるのが相応しいと 考えています。
「お手やわらかに」は、歌謡曲の中では、感情をかなり出してあえてクサく歌ったほうが面白いお色気ソングなので、私にとってはそれほどハードルは高くはないのですが、あくまで リズムと音程をないがしろにしない事を忘れずにいようと心しています。
「プカプカ」は、のたりんとしたメロディとプカプカプカという擬音に 楽天的な楽曲だと誤釈されがちですが、「♪おいら明日死ぬそうな」の辺りからこの楽曲の本質が見え、実はこの曲は、断崖絶壁ぎりぎりの位置に生を留めて立っている女性の歌だという事が判ります。
ですから、「♪おいら明日〜」以前の部分は感情を抑えて、いわば映画のラストが判らないが如くに歌おうと努めています。
「ハイウェイのお月様」。 これも私にとっては そうハードルは高くなく、感情を出して歌うほうが合うバラードです。
「♪暗い暗い暗い道に」で、ぐーっと声を張り、「♪迷わせないで」を囁くように歌おうと考えています。
そして最後に甲斐バンドの楽曲。
私は甲斐よしひろさんの刹那的な世界観というのが無性に好きで、、、というのは、ロックでありながらも非常に歌謡曲的な要素の強いーーー別の言い方をすると、どの楽曲もメロディと詞が見事に合っていて、一曲一曲がそれぞれに、単なるメッセージソングを超えた「詩」「ドラマ」に仕立てられているからです。
テムポが早かったり 三連符が多かったりと、私にとっては大変ハードルが高いのですが、好きさ故に、なんとか練習を重ねて歌えるようになりたいと 切に願っている次第です。
中でも、不良少女の投げやりな哀しさ溢れる「そばかすの天使」は、何としてもモノにしたいところです。
以上が、今年、先ず 私が課題に選んだ十一曲です。
勿論、「感情を控える」というのは、「感情を入れない」「感情を考えない」とは違う訳で、詞全体をまるっと飲み込んで 正しく解釈し、その上で、控える所は控え 出しても良い所・出すべき所は出す、という意味です。
まあ、こんな心構えで、丑年な事だし、牛歩ほどにも前進出来れば、、、と目論んでいます。
カラオケの課題曲・女性歌手の楽曲も加えました [音楽雑記]
ブルースとブルースロックばかりを日頃から聴き愉しみ カラオケでもそれらのジャンルばかりを歌ってきた私・ぼんぼち、昨年は一念発起して 過去記事「今年の抱負ーーーカラオケ三曲」「カラオケの課題曲を増やしました」(十曲)「またカラオケの課題曲を増やしました」(十曲)にも綴ったように、ロックンロールやポップスなどにも挑戦してきました。
が、これらの記事を公開したところ、幾人もの読者のかたから「ぼんぼちさんは女性なのに女性歌手の曲が一つもないんですね」とのご指摘を受けたので、では、今年は女性歌手の楽曲も何曲か歌えるようにしよう!と 以下の五曲を課題とすることにしました。
「私は泣いています」(りりィ)
「怨み節」(梶芽衣子)
「圭子の夢は夜ひらく」(藤圭子)
「サルビアの花」(もとまろ)
「ロックンロールウィドウ」(山口百恵)
先ず、「私は泣いています」は、マイナーコードの 如何にも暗く重い空気感の楽曲。
冒頭で主人公の女性は「♪私は泣いています ベッドの上で」と相手にアピールし、「♪アナタの幸せ願っているわ 私だけはいつまでも」と 思い遣りのある風を装って〆ていますが、私はこれは逆説であり 実は怨み歌、本心では「アナタのことをいつまでも怨んでいるわよぉぉぉ〜〜」といった詞だと解釈しています。
なので、どよんと怨みがましく、特に 各コーラス了りの三音に、その気持ちをねっとりと込めたいと考えています。
次に「怨み節」。
梶芽衣子さん主演の映画「女囚さそり」シリーズの主題歌で、作詞は監督を務められた伊藤俊也氏の みぢんも救いのないどん底に不幸せな女の まさに「怨み節」。
梶芽衣子さんは、ポーンと彼方に放り投げるような歌い方をされていましたが、私は、みしっみしっと 地を這うが如き怨念の塊といった迫り方を目指しています。クサいくらいに。
この時代の歌謡曲には、クサさがよく似合いますね。
三番目には「圭子の夢は夜ひらく」。
この楽曲はタイトルからも判るように、故・藤圭子さんの為に 藤さんの実人生を盛り込んで書き換えられた詞で、藤さんの歌い方以外の 別の側面からの解釈を成り立たせるには どうあがいても無理があると思います。
ですから、私も稚拙ながらも、藤さんが歌っておられた歌い方にほぼ倣う形で、ただ ラストの「♪夢は夜ひ〜ら〜く〜〜」の「♪く〜〜」で、それまでの暗黒さを受け入れて肯定する感情で、少しだけ光りを見せたいと思っています。
四番目には「サルビアの花」。
フォーク好きのかたなら「ああ!懐かしい!!」と声をあげるに違いない 七十年代フォークのヒット曲。
もとまろの三人は、詞の内容よりも メロディーとハモリに重点を置いて歌っていましたが、私は、主人公の 純朴な青年の失恋の切ない気持ちを前面に出して 完成させるつもりです。
私の声質は、青年役を演るのに合っているし、青年の感情に入り込むのも好きなので、違和感なく成立させられそうです。
そして最後に「ロックンロールウィドウ」。
言わずと知れた 山口百恵さんの代表曲の一つですね。
百恵さんは、そのイメージ・品格を損なわないように 凛と歌われていましたが、私は徹底的にロックな歌い方ーーーつまり、蓮っ葉で下品なアバズレ女になりきって歌いたいと 目論んでいます。
以上が、私が今年 稽古し始めている 女性歌手の歌五曲です。
自分の未熟な歌唱力でも形になり、かつ 嗜好的にも歌いたいと思える女性歌手の楽曲は、今のところ この五曲だけです。
なので、昨年課題とした二十三曲に加えて、この五曲も、今年は 愉しみながら稽古に励む心づもりです。
ーーーと、これは余談になりますが、、、
昨年一年間、二日に一度 一日二時間の頻度で稽古をしていたら、右手の親指の右側面の関節の所に ぷっくりとタコが出来てしまいました。
そう、マイクダコです。
私は手汗を非常にかく為、掌でマイクを握ると汗でマイクがツルッと滑ってしまうので、四本の指の指先を揃えて挟むようにして持つのですが、すると必然的に 親指はこの部分が当たってしまうわけです。
たった二日に二時間しか稽古していないのに マイクダコが出来るなんて、真剣に稽古に邁進している人の手には どれほどマイクダコが出来ていることだろう、、、? と思います。
が、これらの記事を公開したところ、幾人もの読者のかたから「ぼんぼちさんは女性なのに女性歌手の曲が一つもないんですね」とのご指摘を受けたので、では、今年は女性歌手の楽曲も何曲か歌えるようにしよう!と 以下の五曲を課題とすることにしました。
「私は泣いています」(りりィ)
「怨み節」(梶芽衣子)
「圭子の夢は夜ひらく」(藤圭子)
「サルビアの花」(もとまろ)
「ロックンロールウィドウ」(山口百恵)
先ず、「私は泣いています」は、マイナーコードの 如何にも暗く重い空気感の楽曲。
冒頭で主人公の女性は「♪私は泣いています ベッドの上で」と相手にアピールし、「♪アナタの幸せ願っているわ 私だけはいつまでも」と 思い遣りのある風を装って〆ていますが、私はこれは逆説であり 実は怨み歌、本心では「アナタのことをいつまでも怨んでいるわよぉぉぉ〜〜」といった詞だと解釈しています。
なので、どよんと怨みがましく、特に 各コーラス了りの三音に、その気持ちをねっとりと込めたいと考えています。
次に「怨み節」。
梶芽衣子さん主演の映画「女囚さそり」シリーズの主題歌で、作詞は監督を務められた伊藤俊也氏の みぢんも救いのないどん底に不幸せな女の まさに「怨み節」。
梶芽衣子さんは、ポーンと彼方に放り投げるような歌い方をされていましたが、私は、みしっみしっと 地を這うが如き怨念の塊といった迫り方を目指しています。クサいくらいに。
この時代の歌謡曲には、クサさがよく似合いますね。
三番目には「圭子の夢は夜ひらく」。
この楽曲はタイトルからも判るように、故・藤圭子さんの為に 藤さんの実人生を盛り込んで書き換えられた詞で、藤さんの歌い方以外の 別の側面からの解釈を成り立たせるには どうあがいても無理があると思います。
ですから、私も稚拙ながらも、藤さんが歌っておられた歌い方にほぼ倣う形で、ただ ラストの「♪夢は夜ひ〜ら〜く〜〜」の「♪く〜〜」で、それまでの暗黒さを受け入れて肯定する感情で、少しだけ光りを見せたいと思っています。
四番目には「サルビアの花」。
フォーク好きのかたなら「ああ!懐かしい!!」と声をあげるに違いない 七十年代フォークのヒット曲。
もとまろの三人は、詞の内容よりも メロディーとハモリに重点を置いて歌っていましたが、私は、主人公の 純朴な青年の失恋の切ない気持ちを前面に出して 完成させるつもりです。
私の声質は、青年役を演るのに合っているし、青年の感情に入り込むのも好きなので、違和感なく成立させられそうです。
そして最後に「ロックンロールウィドウ」。
言わずと知れた 山口百恵さんの代表曲の一つですね。
百恵さんは、そのイメージ・品格を損なわないように 凛と歌われていましたが、私は徹底的にロックな歌い方ーーーつまり、蓮っ葉で下品なアバズレ女になりきって歌いたいと 目論んでいます。
以上が、私が今年 稽古し始めている 女性歌手の歌五曲です。
自分の未熟な歌唱力でも形になり、かつ 嗜好的にも歌いたいと思える女性歌手の楽曲は、今のところ この五曲だけです。
なので、昨年課題とした二十三曲に加えて、この五曲も、今年は 愉しみながら稽古に励む心づもりです。
ーーーと、これは余談になりますが、、、
昨年一年間、二日に一度 一日二時間の頻度で稽古をしていたら、右手の親指の右側面の関節の所に ぷっくりとタコが出来てしまいました。
そう、マイクダコです。
私は手汗を非常にかく為、掌でマイクを握ると汗でマイクがツルッと滑ってしまうので、四本の指の指先を揃えて挟むようにして持つのですが、すると必然的に 親指はこの部分が当たってしまうわけです。
たった二日に二時間しか稽古していないのに マイクダコが出来るなんて、真剣に稽古に邁進している人の手には どれほどマイクダコが出来ていることだろう、、、? と思います。
またカラオケの課題曲を増やしました [音楽雑記]
昨年までは、大好きで日頃からも聴き愉しんでいるジャンルであるブルースとブルースロック(憂歌団 上田正樹と有山淳司 ブルーハーツのマーシーの楽曲)ばかりをカラオケでも歌っていた私・ぼんぼちですが、今年は自分の中の課題として、それ以外のジャンルも 素人の趣味レベルながらも歌えるようになりたいと、ニ日に一度は最寄り駅前のカラオケボックスに通って、過去記事「今年の抱負ーーーカラオケ三曲」「カラオケの課題曲を増やしました」にも綴った通り、計十三曲の稽古に励んでいます。
そして最近は、加えて 以下の十曲も持ち歌に出来れば!と、拙くマイクを握り直しています。
「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」(ダウンタウンブギウギバンド)
「迷惑でしょうが…」(とんねるず)
「なんとなく なんとなく」(スパイダース)
「シーサイドバウンド」(タイガース)
「シー・シー・シー」(タイガース)
「ジンジンバンバン」(タイガース)
「雨あがりの夜空に」(RCサクセション)
「宝くじは買わない」(RCサクセション)
「青い目のHigh School Queen」(チェッカーズ)
「ぐでんぐでん」(萩原健一)
「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」「迷惑でしょうが…」「なんとなく なんとなく」は、皆さんもご存知の通り、台詞の入った楽曲です。
私は、三十代後半から四十代前半まで、あくまで趣味というスタンスでしたが、演技のレッスンを三年半 朗読のレッスンを三年半、それぞれプロの先生について受けており、その間は、毎日 家で自主練を三時間づつやっていたので、台詞部分は、私にとっては それほどハードルの高いものではありません。
どう発すれば成立するのか解りますし、ほぼ 自分の目指した通りに発することが出来ます。
中、「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」は、歌部分がとても少なくて楽ですし、「なんとなく なんとなく」は、順ちゃんのボーカル曲だったので、音楽的に難しくありません。テムポもゆっくりなので、感情も乗せやすいです。
唯一、「迷惑でしょうが…」は、音域が広く 私の声域ではギリギリなので、かなりの稽古が必要だと感じています。
サビの高音部が聴き苦しくなりがちなので、あまり声を張り過ぎずに かつ正確な音程が出せる様に、稽古に稽古を重ねようと考えています。
「シーサイドバウンド」「シー・シー・シー」「ジンジンバンバン」は、タイガース全盛期時代の中でも 特にポップな三曲。
身体全体でリズムを取りながら 聴く人も踊り出したくなるように歌いあげられれば、、、と思っています。
「雨あがりの夜空に」「宝くじは買わない」は、言わずと知れたRCの代表曲。
前者は、音程の正確さばかりに気を取られると 破天荒でエロティックな暗喩曲であるこの楽曲の魅力が半減してしまうので、ロックのココロを最優先させて、ノリにノッて歌い切りたい一曲。
後者は、恋をしている幸せ感溢れる青年の気持ちを描いた フォーク調の作品。
「♪お金で買えないもの」や「♪恋をしているから」といった歌詞を、柔らかく大切にくるんで仕上げたいです。
続いて「青い目のHighi School Queen」は、チェッカーズのドラム 故・クロベエのボーカル曲。
ちなみに、作詞はフミヤさんで 作曲がクロベエです。
典型的な50S調の解りやすい展開で、ややこしいばかりが名曲ではないというお手本の如き楽曲です。
ちょっと切ない歌詞ですが 明るく弾むように歌いとばすのが相応しいので、そのように歌いたいと考えています。
そして最後に「ぐでんぐでん」。
若干 演歌のニュアンスも盛り込まれた 大人の男の哀愁歌。
歌詞の内容に対して意外とテムポが早く 間奏も短いので、感情にとらわれすぎてリズムが遅れをとらないようにと 心がけたいです。
以上が、今回 加え増やした課題曲十曲と、歌うにあたって気をつけたい点です。
これだけ引き出しを作っておけば、忘年会の時にも、皆さんを退屈させずに間を持たせられる、、、かな?
そして最近は、加えて 以下の十曲も持ち歌に出来れば!と、拙くマイクを握り直しています。
「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」(ダウンタウンブギウギバンド)
「迷惑でしょうが…」(とんねるず)
「なんとなく なんとなく」(スパイダース)
「シーサイドバウンド」(タイガース)
「シー・シー・シー」(タイガース)
「ジンジンバンバン」(タイガース)
「雨あがりの夜空に」(RCサクセション)
「宝くじは買わない」(RCサクセション)
「青い目のHigh School Queen」(チェッカーズ)
「ぐでんぐでん」(萩原健一)
「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」「迷惑でしょうが…」「なんとなく なんとなく」は、皆さんもご存知の通り、台詞の入った楽曲です。
私は、三十代後半から四十代前半まで、あくまで趣味というスタンスでしたが、演技のレッスンを三年半 朗読のレッスンを三年半、それぞれプロの先生について受けており、その間は、毎日 家で自主練を三時間づつやっていたので、台詞部分は、私にとっては それほどハードルの高いものではありません。
どう発すれば成立するのか解りますし、ほぼ 自分の目指した通りに発することが出来ます。
中、「港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ」は、歌部分がとても少なくて楽ですし、「なんとなく なんとなく」は、順ちゃんのボーカル曲だったので、音楽的に難しくありません。テムポもゆっくりなので、感情も乗せやすいです。
唯一、「迷惑でしょうが…」は、音域が広く 私の声域ではギリギリなので、かなりの稽古が必要だと感じています。
サビの高音部が聴き苦しくなりがちなので、あまり声を張り過ぎずに かつ正確な音程が出せる様に、稽古に稽古を重ねようと考えています。
「シーサイドバウンド」「シー・シー・シー」「ジンジンバンバン」は、タイガース全盛期時代の中でも 特にポップな三曲。
身体全体でリズムを取りながら 聴く人も踊り出したくなるように歌いあげられれば、、、と思っています。
「雨あがりの夜空に」「宝くじは買わない」は、言わずと知れたRCの代表曲。
前者は、音程の正確さばかりに気を取られると 破天荒でエロティックな暗喩曲であるこの楽曲の魅力が半減してしまうので、ロックのココロを最優先させて、ノリにノッて歌い切りたい一曲。
後者は、恋をしている幸せ感溢れる青年の気持ちを描いた フォーク調の作品。
「♪お金で買えないもの」や「♪恋をしているから」といった歌詞を、柔らかく大切にくるんで仕上げたいです。
続いて「青い目のHighi School Queen」は、チェッカーズのドラム 故・クロベエのボーカル曲。
ちなみに、作詞はフミヤさんで 作曲がクロベエです。
典型的な50S調の解りやすい展開で、ややこしいばかりが名曲ではないというお手本の如き楽曲です。
ちょっと切ない歌詞ですが 明るく弾むように歌いとばすのが相応しいので、そのように歌いたいと考えています。
そして最後に「ぐでんぐでん」。
若干 演歌のニュアンスも盛り込まれた 大人の男の哀愁歌。
歌詞の内容に対して意外とテムポが早く 間奏も短いので、感情にとらわれすぎてリズムが遅れをとらないようにと 心がけたいです。
以上が、今回 加え増やした課題曲十曲と、歌うにあたって気をつけたい点です。
これだけ引き出しを作っておけば、忘年会の時にも、皆さんを退屈させずに間を持たせられる、、、かな?
ムッシュかまやつさんとF-BLOODのファンのリアクションの違い [音楽雑記]
私は、故・ムッシュかまやつさんの音楽の大ファンで、数回ライヴに出向いたことがある。
うち、かまやつさんが60才くらいの頃の、江古田マーキーのライヴでのことだった。
かまやつさんがかつてCMで歌われていた曲を歌う というコーナーで、MC時、かまやつさんはニコニコしながらこう仰った。
「次の曲は、某男性用整髪料のÇMの曲で、、、あの整髪料をつけるとボクみたいに髪がフサフサになる」
「、、、、、、、、、、、、、、」
私は、どういうリアクションを求められているのか判らず、とっさの判断をしかねて凍りついてしまった。
私以外の観客も、私と全く同じ気持ちだったようで、会場全体は水を打った様にシンと静まり返り、観客全員が凍りついていた。
私はかつて、あんなに完全に無音の状態になったライヴハウス会場というものを、後にも先にも体験したことはない。
が、数秒後ーーー
かまやつさんは、会場の温度などまるで感じていない様子でニコニコを続けながら、アコギをメジャーコードでジャカジャカ鳴らし
「♪みっだっれ〜たらっ みっだっれ〜たらっ みっだっれ〜たらっ あっあぁみだれたら〜〜、、、」
と ゴギゲンに歌いはじめられた。
かまやつさんの髪の毛がウイッグだったということは、ファンなら知らぬ者はいない周知の事実で、かまやつさんご自身もインタビューで「これ、ウイッグですよ」と答えておられたこともあったというし、マチャアキに笑い話にされたこともあった様だ。
そのライヴの日の4日前に「笑っていいとも!」の電話のコーナーに出演されていたが、ライヴの日の髪の毛は4日前より20センチは長かった。
だから、あのMÇは、かまやつさんご本人としては、明るく笑い飛ばしてほしかったのだろうな、、、と 後日 気がついた。
一方ーーー
私は、小柄で華奢な体型でネズミさんみたいなお顔立ちの男性が好みのルックスなので、そこにピタリと当てはまる 若かった頃の藤井フミヤさんのルックスが大好きである。
ファンというわけではないが、若かった頃のフミヤさん観たさに、しょっちゅうyoutubeを覗いている。
と、つい最近ーーー
F-BLOODがkinki kidsの番組にゲスト出演している動画が出てきた。
観ていると、トークの時間に「昔は、兄・フミヤさんの服を弟・尚之さんがよく着ていた」という話になった。
するうち尚之さんは「でも、いつの間にか着れなくなっちゃって」と 仰った。
ーーーフミヤさんは身長160ちょっとと小さく、尚之さんは170ちょっとと平均的身長なので、自分が大きくなったためにお兄さんの服は小さくて着られなくなってしまった という意味である。
と、その瞬間、スタジオの観客一同が、キュー出しされた様に揃って「どわわわーーーっ!」と 大爆笑した。
司会進行役のkinkiの片方の人が「えっ?、、、あっ! あ〜〜あ」(何で笑ってるの?、、、あっ!なるほど、そういう意味で笑ってるのね!)という表情と動きをしたら、輪をかけて「どわわわわーーーーつ!!!」と より一層の大爆笑となった。
フミヤさんは、最初の大爆笑も kinkiの片方の人の表情・動きも 輪をかけた大爆笑も 何もなかったかの如きすましたお顔でスルーされていて、笑いがひとしきり収まったタイミングで「ど れ に し よ う か なーって、俺の服、勝手に着て行くんですよー」と ご自身の服を尚之さんがまだ着ることが出来た時代の話に戻された。
フミヤさんが小さいことは一目瞭然だし、チェッカーズ時代、とんねるずとのコントで 小さいことをやたらイジられたり 台詞でも自ら「小さいけど○○です」と言わされたりしていたが、あのトークでの尚之さんの言い方は、明らかに 笑いを取る目的の言い方ではなかったと思う。
私は別に、かまやつさんのファンが私を含めて狙いを読めないと反省しているわけでもないし、F-BLOODのファンが気遣いに欠けていると責めているわけでもない。
ーーーファンというのはどうしてこうも、それぞれのミュージシャンによってリアクションが激しく違い 何の打ち合わせもしていないのにピタリと揃うのだろう?と 不思議に感じずにおれないのである。
生まれて初めて買ったレコードーーー「危険なふたり」 [音楽雑記]
みなさんは、生まれて初めて買ったレコードって何でやすか?
あっし・ぼんぼちは、ジュリーの「危険なふたり」でやす。
ーーーあれは、あっしが小学五年の時でやした。
あっしは幼い頃から、小柄できゃしゃな体型でネズミさんみたいなお顔立ちの男性がタイプだったので、当時は、あいざき進也さんがその条件にピタリと当てはまっていて 100%好きなルックスだったのでやすが、衣装のデザインや 楽曲や いかにもアイドルですよ!という演出が好きになれなかったために、ファンにはなれやせんでやした。
で、衣装 楽曲 ルックス イメージ作りの演出など、すべての要素の総合得点が、あっしがファンになれる得点に達していたのがジュリーでやした。
その頃のジュリーは、アイドル タイガースを卒業し PYGを経てピンになり、もうアイドルとは呼ばせない!大人の女性のファンを獲得するんだ!といった戦略の真っ只中でやした。
不倫をテーマとした楽曲を何曲も出し、その何曲目かに発売されたのが「危険なふたり」でやした。
家庭のある年上の女性に本気で恋する若い青年。
青年側からは彼女が遊びであることなどまるで見えずに 自分と同じ気持ちだと信じてやまない。
そんな馬車馬的な青年の感情を 当時の大人気作詞家・安井かずみさんが見事に描ききった秀逸な歌詞でやす。
小五のあっしには この歌詞の意味など解かろう筈もなく「なんだか訳の解らない変な詞だなあ」と思いやした。
けれど、東海林修さんの、ちょっとだけロックを彷彿とさせる軽妙なアレンジと 加瀬邦彦さんの、単純でありながらもノリのいいメジャーコードのメロディーには、理屈抜きに惹かれるものがありやした。
それを、ジュリーが、大きな造花を胸に付けたスーツで くねくねと中性的に動き 柔らかに歌う様は、あっしの中で非常に高い得点となりやした。
それで、「危険なふたり」を、自分のお小遣いの中から 強い意志で以てレコード屋さんに出向いて求めた というわけでやす。
こうして熱心なジュリーファンになったあっしは、ジュリーのどこに特に高得点を入れずにはおれなかったかというと、「退廃的な雰囲気」でやした。
朽ちてゆくもの 陽の当たらないもの 湿ったもの に惹かれてやまないと事あるごとに仰っていた TBS(その後は独立されてカノックス)プロデューサーであった久世光彦さんや 反体制を通底するテーマとして尋常ならざる負のエネルギーで表現されていたゴジさん(長谷川和彦監督)らと組んだ仕事や レトロ・退廃のイメージを得意とする堀切ミロさんのスタイリングが、ジュリーという素材を「完璧な生きる退廃美」として創り出していやした。
中でも あっしは、堀切ミロさんのスタイリングは、将来 自分もこんなスタイリストになりたいと憧れ続けるほどに好きで、ミロさんがお仕事なさった雑誌は何冊も所有していやした。
けれどーーー
そのうちジュリーは、久世さんともゴジさんとも仕事を共にしないようになり、スタイリストも堀切ミロさんから早川タケジさんに替わってしまいやした。
早川タケジさんのスタイリングは、落下傘を背負った真っ赤な衣装の「TOKIO」に代表されるポップな世界観でやす。
よって、ジュリーのイメージそのものも、退廃からポップへと変貌してしまいやした。
あっしは勿論 早川さんも素晴らしいスタイリスト(本業はイラストレーター)だと認めてはいやすが、好き嫌いで言うと ポップな方向性は好きにはなれないので、あっしの中で ジュリーの好きになれる重要な要素が0点になってしまったので、ジュリーファンではいられなくなってしまいやした。
ネットもなく「好きになれる もの・人物」が滅多に見つからず、日々 精神的に飢餓状態であった十代の頃、「危険なふたり」で熱心なファンになれた退廃的だった時代のジュリーは、あっしの精神的飢餓を埋め合わせてくれた 数少ない貴重な存在だったと、当時のジュリーや それを創り出したブレーン一同様に感謝していやす。
カラオケの課題曲を増やしました [音楽雑記]
下手の横好きでカラオケを二日に一度は歌いに通っている 私・ぼんぼち、過去記事にも書きましたように、元々 ブルースとブルースロックが好きで、憂歌団 上田正樹と有山淳司 ブルーハーツの楽曲ばかりを歌ってきました。
が、今年の初頭から 他のジャンルも歌えるようになりたいと、先ず ハードルの低い「みかん色の恋」(ずうとるび) 「NAINAI16」(しぶガキ隊) 「100%・・・SOかもね!」(しぶガキ隊)の三曲の練習を積み、何とか形がつくくらいに歌えるようになりました。
ということで、今度はもう少しだけハードルの高い 以下の十曲を稽古することに決めました。
「上を向いて歩こう」(RCサクセション)
「ファンキー モンキー ベイビー」(キャロル)
「ヘイ タクシー」(キャロル)
「ルイジアンナ」(キャロル)
「シンデレラ」(クールス)
「スモーキン ブギ」(ダウンタウンブギウギバンド)
「大阪で生まれた女」(萩原健一)
「恋のレッツダンス」(チェッカーズ)
「お前が嫌いだ」(チェッカーズ)
「渚のdance hall」(チェッカーズ)
先ず、「上を向いて歩こう」は、日本のみならず海外でも「スキヤキソング」としてヒットした かの日本の戦後の国民的流行歌をキヨシローがロックバージョンでカバーしたもので、私は、キヨシローほどメロディーを変えて歌いませんが、ロックのココロで全身で以て声を飛ばして 詞の意味を訴えたいと思います。
「ファンキー モンキー ベイビー」から「スモーキン ブギ」までの五曲は、典型的なロックンロールです。
ツイストを踊る気分でノリノリで 聴く人が楽しくなるように歌えれば、、、と思います。
中でも「スモーキン ブギ」は、歌詞がとてもユニークで、他愛ない憎めない不良!といった感じが出せれば、、、と考えています。
次に「大阪で生まれた女」ですが、あえて元祖BOROバージョンではなくショーケンバージョンを選んだ理由は、こちらのほうがテムポがゆっくりで 感情を乗せやすいからです。
「♪電信柱に染み付いた夜」や「♪裸電球をつけたけどまた消して」などと、この楽曲は暗喩的表現がそこここに盛り込まれていて、詞の向こう側にある意味を理解できないと成立させられないので、向こう側の意味を頭に思い描きながら歌いたいです。
また、この詞全体から浮かび上がってくる主人公の女性像から 「♪あなた」ではなく「♪あんた」と歌ったほうが、より らしい世界観が表現できると判断したので、そう歌おうと思っています。
「恋のレッツダンス」は、アップテンポのダンスナンバー。
チェッカーズがアマチュア時代に作った楽曲「レッツ ザ ダンス」に詞だけを作詞家の先生が書き換えたもののようです。
「レッツ ザ ダンス」の詞は、様々なダンスを次々と踊り楽しむことがテーマになっていますが、こちらは恋の展開が中心になっています。
「レッツ ザ ダンス」もゴキゲンな歌詞なので、もしもそちらもカラオケに入っていたなら、歌い比べて感情の乗せ方の違いを楽しんでみたかったところです。
「お前が嫌いだ」は、タイトルからして何とも面白いロックナンバー。
詞の内容は、本当は大好きで仕方がない女の子に ふにゃふにゃに骨抜きにされる 自称イケてる男の子の素直になれない感情を 逆説的にぶつけたもの。
曲中に三度出てくる「♪おーまーえーがー きーらーいーだっ!」を、嬉しそうに あかんべーしているようなつもりで歌い切りたいと考えています。
ちなみに作詞者は藤井フミヤさんで、フミヤさんの先鋭的な着眼点には脱帽です。
そして最後に「渚のdance hall」ですが、これは腹の底からたっぷりと声量を使って歌いあげるタイプのバラード曲です。
砂浜をステージに 降り注ぐ星星をミラーボールに見立て、別れのチークダンスを踊る二人、、、
ワンコーラス目に「♪どうして泣いてるの?ふられたのは僕さ」という詞が出てくるのですが、この一節には、「これほど男の優しさが凝縮された言葉は他にないぞ!」と ぐっと来ずにはおれませんでした。
よく役者が「あまりにも魅力ある台詞が一つあったために この役をやろうと決めた」と言いますが、この歌を歌い込もうと決めた私の心情も それに近いものがあると言えます。
この曲の作詞も、フミヤさんです。
と まあ、こんな理論・心構えで 以上十曲を、所詮は素人のお遊びレベルにすぎませんが、楽しみながらも一生懸命に 練習してゆくつもりです。
今年いっぱいには、この十曲が、なんとか人前でお披露目しても恥ずかしくない程度になれば、、、と思っています。
が、今年の初頭から 他のジャンルも歌えるようになりたいと、先ず ハードルの低い「みかん色の恋」(ずうとるび) 「NAINAI16」(しぶガキ隊) 「100%・・・SOかもね!」(しぶガキ隊)の三曲の練習を積み、何とか形がつくくらいに歌えるようになりました。
ということで、今度はもう少しだけハードルの高い 以下の十曲を稽古することに決めました。
「上を向いて歩こう」(RCサクセション)
「ファンキー モンキー ベイビー」(キャロル)
「ヘイ タクシー」(キャロル)
「ルイジアンナ」(キャロル)
「シンデレラ」(クールス)
「スモーキン ブギ」(ダウンタウンブギウギバンド)
「大阪で生まれた女」(萩原健一)
「恋のレッツダンス」(チェッカーズ)
「お前が嫌いだ」(チェッカーズ)
「渚のdance hall」(チェッカーズ)
先ず、「上を向いて歩こう」は、日本のみならず海外でも「スキヤキソング」としてヒットした かの日本の戦後の国民的流行歌をキヨシローがロックバージョンでカバーしたもので、私は、キヨシローほどメロディーを変えて歌いませんが、ロックのココロで全身で以て声を飛ばして 詞の意味を訴えたいと思います。
「ファンキー モンキー ベイビー」から「スモーキン ブギ」までの五曲は、典型的なロックンロールです。
ツイストを踊る気分でノリノリで 聴く人が楽しくなるように歌えれば、、、と思います。
中でも「スモーキン ブギ」は、歌詞がとてもユニークで、他愛ない憎めない不良!といった感じが出せれば、、、と考えています。
次に「大阪で生まれた女」ですが、あえて元祖BOROバージョンではなくショーケンバージョンを選んだ理由は、こちらのほうがテムポがゆっくりで 感情を乗せやすいからです。
「♪電信柱に染み付いた夜」や「♪裸電球をつけたけどまた消して」などと、この楽曲は暗喩的表現がそこここに盛り込まれていて、詞の向こう側にある意味を理解できないと成立させられないので、向こう側の意味を頭に思い描きながら歌いたいです。
また、この詞全体から浮かび上がってくる主人公の女性像から 「♪あなた」ではなく「♪あんた」と歌ったほうが、より らしい世界観が表現できると判断したので、そう歌おうと思っています。
「恋のレッツダンス」は、アップテンポのダンスナンバー。
チェッカーズがアマチュア時代に作った楽曲「レッツ ザ ダンス」に詞だけを作詞家の先生が書き換えたもののようです。
「レッツ ザ ダンス」の詞は、様々なダンスを次々と踊り楽しむことがテーマになっていますが、こちらは恋の展開が中心になっています。
「レッツ ザ ダンス」もゴキゲンな歌詞なので、もしもそちらもカラオケに入っていたなら、歌い比べて感情の乗せ方の違いを楽しんでみたかったところです。
「お前が嫌いだ」は、タイトルからして何とも面白いロックナンバー。
詞の内容は、本当は大好きで仕方がない女の子に ふにゃふにゃに骨抜きにされる 自称イケてる男の子の素直になれない感情を 逆説的にぶつけたもの。
曲中に三度出てくる「♪おーまーえーがー きーらーいーだっ!」を、嬉しそうに あかんべーしているようなつもりで歌い切りたいと考えています。
ちなみに作詞者は藤井フミヤさんで、フミヤさんの先鋭的な着眼点には脱帽です。
そして最後に「渚のdance hall」ですが、これは腹の底からたっぷりと声量を使って歌いあげるタイプのバラード曲です。
砂浜をステージに 降り注ぐ星星をミラーボールに見立て、別れのチークダンスを踊る二人、、、
ワンコーラス目に「♪どうして泣いてるの?ふられたのは僕さ」という詞が出てくるのですが、この一節には、「これほど男の優しさが凝縮された言葉は他にないぞ!」と ぐっと来ずにはおれませんでした。
よく役者が「あまりにも魅力ある台詞が一つあったために この役をやろうと決めた」と言いますが、この歌を歌い込もうと決めた私の心情も それに近いものがあると言えます。
この曲の作詞も、フミヤさんです。
と まあ、こんな理論・心構えで 以上十曲を、所詮は素人のお遊びレベルにすぎませんが、楽しみながらも一生懸命に 練習してゆくつもりです。
今年いっぱいには、この十曲が、なんとか人前でお披露目しても恥ずかしくない程度になれば、、、と思っています。
好きなバンドの音楽の方向性が変わってしまいました [音楽雑記]
先日の1月17日、大好きな某バンドの日本武道館ライヴに出掛けてきました。
2011年の第一回目 2015年の第二回目に続き、今回は第三回目の公演・鑑賞でした。
あくまで主観ですが、感想を述べさせていただくと----
酷くがっかり・・・・・・大きく失望してしまいました。
そして、もうこのバンドのファンでいるのは辞めようと思いました。
決して、間違っても 歌や演奏のクオリティが低下したのではありません。
では、私はどこに失望してしまったかというと----
そのバンドは毎回 60年代ロックンロールのカバー&60年代ロックンロール調オリジナル楽曲を演っていたのですが、今回の武道館公演では、カバーが一曲だけで しかもビートルズの代表曲をほんのサワリだけちょっと奏でただけで あとは全てオリジナルだったのです。
しかも、オリジナルも作りたての頃とは大きく違い 60年代色が殆ど感じられないテムポと音で、もはや イマドキのありきたりの普通のロック といった仕上げ方でした。
以下は私の推測ですが----
バンドのメンバーは本心としては、これからも忠実に60年代ロックンロールを演り続けてゆきたかったと察します。
けれど全国的に人気者になって多くのファンを確保し続けてゆくには、今回のようなイマドキのありきたりの つまり大衆受けするロックに走らざるを得なかったのだと思います。
メンバーも三十代半ばになり、中には結婚して子供のいる人もいます。 近い将来、全員がそういう状況になるでしょう。
その為には、これから先 何十年間も、ある程度以上の安定した収入を得続けなければならないのです。
したがって、全国区で大衆に売れ続けることをしなければならないのです。
私は十八才から二十六才までの間、母親を養う為に画家をやっていたのですが、母親を養えるだけの安定した収入を得なければならない為に、描きたくもない自分の大嫌いな画風の作品を描いていたので、現在のメンバーの置かれている立場・心境が痛いほど解かります。
それはとても、辛く苦しく 理不尽さに満ち満ちたことです。
しかし、そういった現実を飲みこんでゆかなければ ある程度以上の安定した収入は得られないのです。
いかなる分野の表現者も、資本主義社会の外側でカスミを食っては生きてゆけないのです。
だから、私はメンバーを責める気持ちにはなれません。
とても気の毒に思います。
思い返すと、私がこのバンドのファンになったのは、第一回目の武道館ライヴに行く一年くらい前でしたから 約八年間ファンでいた計算になります。
今まで私が好きになったバンドは、大昔に解散してしまっていたり すでにメンバーが亡くなっていたりで、リアルタイムでここまで夢中になれたバンドは、このバンドが生まれて初めてでした。
第一回目の武道館では、リアルタイムで生で60年代の音が聴けることに 涙が出るほど感激しました。
二度目の武道館では、アリーナ席の一列目で、しかも私がメンバーの中でも一番好きな ギター&コーラスのJさんのまん前の席で、失神しそうに興奮しました。
加えて、ハウリンウルフの声を模倣したというボーカルのRさんの声も間近で聴けて、その底力に感服しました。
四人のメンバーさん、私はこれでファンを辞めますが、皆さんが私に与えてくださった幸せは一生忘れません。
本当にハッピーな八年間でした。
これからも理不尽なことを山ほど飲みこんでゆかなければならないのは必至でしょうけれど、頑張って現実と戦ってください。
Jさん Rさん Tさん Mさん、ありがとう! ありがとう!! ありがとう!!!
そして、さようなら! さようなら!! さようなら!!!
(画像は、今回のライヴ終盤でアリーナ席に降り注いだ たくさんの銀色のテープです)
今年の抱負---カラオケ三曲 [音楽雑記]
みなさんは、今年の抱負って 何かお持ちですか?
私・ぼんぼちは、カラオケで 新たな曲を三曲 歌えるようにすることが、今年の抱負です。
今まで私は、ブルースやブルースロックが好きで、そういうジャンルばかりを歌ってきました。
具体的に挙げると----
憂歌団 上田正樹と有山淳司 ブルーハーツのアルバムの中のマーシーの作った曲、です。
好きなジャンルなのでココロがすっと入ってゆけるというのもありますが、ブルースやブルースロックというジャンルは、リズムや音程よりも感情・言葉を前面に出してしまえば成立させてしまえる という面があります。-----勿論、素人の趣味レベルでのスタンスですが。
 私は以前、趣味で演技のレッスンを受けていて、その中に「歌という手段を使って表現をする」という科目もあったので、詞の意味・言はむとしている内容・感情を正しく聴き手に届かせる という訓練は、多少なりともしてきました。
私は以前、趣味で演技のレッスンを受けていて、その中に「歌という手段を使って表現をする」という科目もあったので、詞の意味・言はむとしている内容・感情を正しく聴き手に届かせる という訓練は、多少なりともしてきました。
そういった観点からも、ブルース ブルースロックというのは、レッスンでお習いしたことをそのまま活かせて 歌い易かったのです。
が、聴いている側は、「はぁ~ またこーいう曲かぁ」と退屈するだろうし、自分でも ちょっと違うジャンルの曲にも挑戦してみたいな という気持ちもあり、以下の三曲を 今年の課題曲とすることにしました。
「みかん色の恋」 (詞・岡田冨美子 曲・佐瀬寿一 元歌歌唱・ずうとるび)
「NAI-NAI16」 (詞・森雪之丞 曲・井上大輔 元歌歌唱・シブがき隊)
「100%・・・Soかもね!」 (詞・森雪之丞 曲・井上大輔 元歌歌唱・シブがき隊)
何故、この三曲を選んだかというと----
先ず、第一に、ハードルが低い ということです。
カラオケは遊びなんだから どんな曲だって 歌いたいと思えば好き勝手に無手勝流に楽しめばいいじゃないか!という声が多数 聞こえてきそうですが、どうも私の性分としては それは嫌なのです。
越えられないハードルをなぎ倒しながら走ってゆく というのは、自分自身が気持ちが悪くて楽しくないのです。
勿論、越えられるハードル設定は、素人の趣味スタンスの低さですが、低いハードルをきちんきちんと越えることに 私は達成感・楽しさを覚えるのです。
 そして第二に----
そして第二に----
三曲とも 詞に強烈な魅力を感じていることです。
いずれも、十代半ばの少年の 異姓への心情を絶妙に表現したものですが----
「みかん色の恋」は、キスの経験もないウブな男の子が 好きな少女との距離を縮めてゆく幸せ感に溢れる内容で、「みかん色」というのは「幸せ色」という意味です。
冒頭は弾むようにとにかく明るく サビ部分では彼方に伸びるように歌ってゆければ・・・・と思っています。
「NAI-NAI16」は、まだ心と肉体のバランスを巧く取れずにいる少年の やるせない はやる心を描いた作品です。
幾度も繰り返される「ナイナイナイ・・・・・」に、少年の切なさを託せれば・・・・と考えています。
「100%・・・Soかもね!」は、「NAI-NAI16」の主人公よりほんの少しだけ大人になった 揺れ動いた末に「これは恋だ!」と自覚する少年の歌です。
少年の心の中に小爆発を起こす感情の「バン!バン!バン!!!」「ストップ!ストップ!ストップ!!!」を印象強く伝えられれば・・・・と稽古しています。
第三には----
これら三曲は、単に詞が優れているのみならず、詞の感情とメロディーが見事に一致している ということにあります。
近年は特に、詞とメロディーが一致していない歌というのが目立ちますが、私はああいった歌は、いくらメロディーだけが良くても好きにはなれません。
私は歌というものは、あくまでも 詞の意味・感情を聴き手に伝えてこそだと考えています。
これら三曲は、無理なく自然と 感情を乗せ易いメロディーに計算されつくして仕立てられています。
第四は----
私は個人的に、十代半ばの少年役を演じるのが 無性に好きなのです。
自分と全く違う人物になれるという所が、仮装を楽しむのと同じ理屈で ストレス発散になるからです。
又、声質や声のトーンの面でも向いているようで、「NAI-NAI16」と「100%・・・Soかもね!」は原曲より♯3 「みかん色の恋」は♯1で ちょうど良く歌えるキーになります。
幾度も繰り返し書いていますが、あくまで所詮は素人の趣味レベルなので、自分で「成立した」と合格点を出しても それなりのものであることは必至ですが、今年は、この三曲を歌えるようにすることが、私・ぼんぼちのささやかな抱負です。
私・ぼんぼちは、カラオケで 新たな曲を三曲 歌えるようにすることが、今年の抱負です。
今まで私は、ブルースやブルースロックが好きで、そういうジャンルばかりを歌ってきました。
具体的に挙げると----
憂歌団 上田正樹と有山淳司 ブルーハーツのアルバムの中のマーシーの作った曲、です。
好きなジャンルなのでココロがすっと入ってゆけるというのもありますが、ブルースやブルースロックというジャンルは、リズムや音程よりも感情・言葉を前面に出してしまえば成立させてしまえる という面があります。-----勿論、素人の趣味レベルでのスタンスですが。
そういった観点からも、ブルース ブルースロックというのは、レッスンでお習いしたことをそのまま活かせて 歌い易かったのです。
が、聴いている側は、「はぁ~ またこーいう曲かぁ」と退屈するだろうし、自分でも ちょっと違うジャンルの曲にも挑戦してみたいな という気持ちもあり、以下の三曲を 今年の課題曲とすることにしました。
「みかん色の恋」 (詞・岡田冨美子 曲・佐瀬寿一 元歌歌唱・ずうとるび)
「NAI-NAI16」 (詞・森雪之丞 曲・井上大輔 元歌歌唱・シブがき隊)
「100%・・・Soかもね!」 (詞・森雪之丞 曲・井上大輔 元歌歌唱・シブがき隊)
何故、この三曲を選んだかというと----
先ず、第一に、ハードルが低い ということです。
カラオケは遊びなんだから どんな曲だって 歌いたいと思えば好き勝手に無手勝流に楽しめばいいじゃないか!という声が多数 聞こえてきそうですが、どうも私の性分としては それは嫌なのです。
越えられないハードルをなぎ倒しながら走ってゆく というのは、自分自身が気持ちが悪くて楽しくないのです。
勿論、越えられるハードル設定は、素人の趣味スタンスの低さですが、低いハードルをきちんきちんと越えることに 私は達成感・楽しさを覚えるのです。
三曲とも 詞に強烈な魅力を感じていることです。
いずれも、十代半ばの少年の 異姓への心情を絶妙に表現したものですが----
「みかん色の恋」は、キスの経験もないウブな男の子が 好きな少女との距離を縮めてゆく幸せ感に溢れる内容で、「みかん色」というのは「幸せ色」という意味です。
冒頭は弾むようにとにかく明るく サビ部分では彼方に伸びるように歌ってゆければ・・・・と思っています。
「NAI-NAI16」は、まだ心と肉体のバランスを巧く取れずにいる少年の やるせない はやる心を描いた作品です。
幾度も繰り返される「ナイナイナイ・・・・・」に、少年の切なさを託せれば・・・・と考えています。
「100%・・・Soかもね!」は、「NAI-NAI16」の主人公よりほんの少しだけ大人になった 揺れ動いた末に「これは恋だ!」と自覚する少年の歌です。
少年の心の中に小爆発を起こす感情の「バン!バン!バン!!!」「ストップ!ストップ!ストップ!!!」を印象強く伝えられれば・・・・と稽古しています。
第三には----
これら三曲は、単に詞が優れているのみならず、詞の感情とメロディーが見事に一致している ということにあります。
近年は特に、詞とメロディーが一致していない歌というのが目立ちますが、私はああいった歌は、いくらメロディーだけが良くても好きにはなれません。
私は歌というものは、あくまでも 詞の意味・感情を聴き手に伝えてこそだと考えています。
これら三曲は、無理なく自然と 感情を乗せ易いメロディーに計算されつくして仕立てられています。
第四は----
私は個人的に、十代半ばの少年役を演じるのが 無性に好きなのです。
自分と全く違う人物になれるという所が、仮装を楽しむのと同じ理屈で ストレス発散になるからです。
又、声質や声のトーンの面でも向いているようで、「NAI-NAI16」と「100%・・・Soかもね!」は原曲より♯3 「みかん色の恋」は♯1で ちょうど良く歌えるキーになります。
幾度も繰り返し書いていますが、あくまで所詮は素人の趣味レベルなので、自分で「成立した」と合格点を出しても それなりのものであることは必至ですが、今年は、この三曲を歌えるようにすることが、私・ぼんぼちのささやかな抱負です。