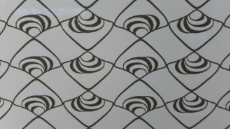ぼんぼち・人生の新章 [独り言]
一月の演技のレッスンを最後にすっかり気が済んで、レッスンに通う事をやめた私・ぼんぼち、早くも次にやりたい事が浮上し、これからは、それに邁進したいと思っています。
それは何かというとーーー
「写真作品として完成度の高いセルフポートレートを月一のペースでアップする事」です。
なんだ、セルフポートレートなんて、今までも何枚も挙げてきたじゃん、って思われたかたも多いと察しますが、今までは、「もっと引きで撮りたいけど、これ以上引くとスマホの影が入っちゃうー」とか、部屋の場所によっては、薄暗ーい仕上がりになってしまって、それでも「まっ、いっか」と、イマイチ イマニ イマサンの、とても「作品」と言えるようなものではなく、単なる個人の記録レベルのセルフポートレートが多かったんです。
ーーー「作品」と自分で言えるのは、三枚くらい。
なのでこれからは、自分の中での合格レベルを厳しくして、「作品」と呼べるものだけを公開してゆこうと決めました。
そのために、スマホ自撮り時にスマホに装着するリング状のライトを購入しました。
何故、新章の課題がこれかというとーーー
ぼんぼちは、若い頃の写真って、殆どないんですよ。
若い頃は、顔中のニキビとブルドックさながらにたるんだ顔で、「こんな自分の顔、嫌っ!!!」と、泣きながら破り捨ててしまっていたんです。
遺してあるのは、画家時代、個展を開いた時に、作品とともに画商が写した記録写真だけ。
それに人間って誰しも、明日どうなるか判らないじゃないですか。
今日と同じ自分が明日も存在していられる保証なんて、どこにもない。
だから、ニキビ&ブルドックでなくなった今、「ぼんぼちが生きた証」を、自分なりの最上級の状態で、一枚でも多く遺しておきたいんです。
自撮りライト、まだ試していませんが、これまで公開したお粗末な数々よりは、間違いなくクオリティーの高いものが撮れるでしょう。
堂々と、「これは写真作品です!」と言えるセルフポートレートが撮れるように、頑張るぞっ!!!
もう一度、大阪に行きたかったけど [独り言]
大阪って、ぼんぼちにとっては聖地なんだよね。
何故かというと、ぼんぼちは、憂歌団や上田正樹さんらのナニワブルースが大好きだから。
で、三十代半ばに、憧れの大阪に行ったんだけどね。
それはもぅ、イメージと寸分たがわぬ良き地だったよ。
繁華街を流れる幾筋もの川、コリアンタウン、悲しい色をした海、、、
で、死ぬまでにもう一度、大阪に旅したいと思い続けてたんだけどね。
残念だけど、無理、、、、、
理由は、何日間も連続で一日中街を歩き回る体力がなくなってしまったから。
せっかく行ったなら、毎日、朝から晩まで遊びまわりたいじゃない?
でももぅ、とてもとても、、、
どのくらい体力がなくなってしまったかというと、都内の一時間以内で到着できる街に行って、二十分歩いて喫茶店に寄って、また二十分歩いて喫茶店で休憩して、また二十分歩いて早い時間から営ってる飲み屋さんでビール二本で終了。
次の日、ダウン。
ね、これじゃ、大阪行きは無理でしょ。
思ってたより早く、身体の老い、来ちゃったな。
五十代のうちに、大阪再訪しておけば良かったな。
今は、三十代の時に巡った 主にミナミの街街を、頭蓋の中で反芻して、「あー、満喫したなー」と目をつむるばかりだよ、、、、、
何故かというと、ぼんぼちは、憂歌団や上田正樹さんらのナニワブルースが大好きだから。
で、三十代半ばに、憧れの大阪に行ったんだけどね。
それはもぅ、イメージと寸分たがわぬ良き地だったよ。
繁華街を流れる幾筋もの川、コリアンタウン、悲しい色をした海、、、
で、死ぬまでにもう一度、大阪に旅したいと思い続けてたんだけどね。
残念だけど、無理、、、、、
理由は、何日間も連続で一日中街を歩き回る体力がなくなってしまったから。
せっかく行ったなら、毎日、朝から晩まで遊びまわりたいじゃない?
でももぅ、とてもとても、、、
どのくらい体力がなくなってしまったかというと、都内の一時間以内で到着できる街に行って、二十分歩いて喫茶店に寄って、また二十分歩いて喫茶店で休憩して、また二十分歩いて早い時間から営ってる飲み屋さんでビール二本で終了。
次の日、ダウン。
ね、これじゃ、大阪行きは無理でしょ。
思ってたより早く、身体の老い、来ちゃったな。
五十代のうちに、大阪再訪しておけば良かったな。
今は、三十代の時に巡った 主にミナミの街街を、頭蓋の中で反芻して、「あー、満喫したなー」と目をつむるばかりだよ、、、、、
「けっこう」は死語になりつつあるようだ [独り言]
私は喫茶店やカフェでコーヒーを飲む時はブラックで飲むので、一緒に持って来ていただいた砂糖とミルクはお断りしている。
その時、「いらないです」「大丈夫です」「けっこうです」のいずれかの言い方を使っているのだが、どうやら、最近の若い店員さんには「けっこうです」は、通じにくくなりつつあるのを感じている。
掌を押し出すアクションをしながら「けっこうです」
一瞬、戸惑った表情をされ
「、、、、? いらない、、、ですか?」
「、、、、あ、、大丈夫、、、ですか?」と。
「いらないです」や「大丈夫です」と言った時には すんなりと「はい!」と笑顔で盆に戻してくださる。
確かに「けっこう」という言葉はややこしい語ではある。
「けっこうなご趣味ですね」という時の様な「良い」「素晴らしい」という意味と、「いらない」という意味との二種類があるからである。
昭和人間の私は、「けっこうです」は、最も丁寧な断り方だと思っているのだが、今の若者には、通じなかったり、あるいは、冷たい突き放す様な印象を与えてしまう様だ、と、彼らのリアクションから読み取れる。
言葉は生き物なので、日々 変化をし続けている。
で、あるから、私はこれからは、店員さんが若い人だった場合は、「けっこうです」は使わずに、「いらないです」「大丈夫です」のどちらかを使って、若い店員さんとも円滑なコミニュケーションが取れる様にしようと考えている。
その時、「いらないです」「大丈夫です」「けっこうです」のいずれかの言い方を使っているのだが、どうやら、最近の若い店員さんには「けっこうです」は、通じにくくなりつつあるのを感じている。
掌を押し出すアクションをしながら「けっこうです」
一瞬、戸惑った表情をされ
「、、、、? いらない、、、ですか?」
「、、、、あ、、大丈夫、、、ですか?」と。
「いらないです」や「大丈夫です」と言った時には すんなりと「はい!」と笑顔で盆に戻してくださる。
確かに「けっこう」という言葉はややこしい語ではある。
「けっこうなご趣味ですね」という時の様な「良い」「素晴らしい」という意味と、「いらない」という意味との二種類があるからである。
昭和人間の私は、「けっこうです」は、最も丁寧な断り方だと思っているのだが、今の若者には、通じなかったり、あるいは、冷たい突き放す様な印象を与えてしまう様だ、と、彼らのリアクションから読み取れる。
言葉は生き物なので、日々 変化をし続けている。
で、あるから、私はこれからは、店員さんが若い人だった場合は、「けっこうです」は使わずに、「いらないです」「大丈夫です」のどちらかを使って、若い店員さんとも円滑なコミニュケーションが取れる様にしようと考えている。
うざかったおっさんK氏が虹の橋を渡ってしまった [独り言]
飲み仲間だったK氏が、一月頭に 虹の橋を渡ってしまった。
癌だったという。
今の時代、癌は、必ずしも死に直結する病いではなくなったが、K氏はそれが理由で、虹の橋を渡ることとなってしまった。
私の記憶が間違っていなければ、二年ほど前から「身体の調子が良くない」と、私達とも、一人でも、飲みに行かなくなっていた。
K氏とは、我らがSSブロガーR氏を通じて知り合った人物だった。
逢う度に私に、「レズビアンの人にモテそうな感じー!」とか、「(カラオケで『恨み節』を歌うと)恨み節って感じー!」とか、「(お笑い芸人の)鳥居みゆきに似てるー!」とか、およそ褒め言葉とは縁遠い台詞をひっきりなしに次から次へとふっかけてきていた。
私は正直、よくもまあ、こうもヘンテコな形容ばかりを並べ立てることの出来る うざいおっさんだなあと、煙たく思っていた。
ある時、カラオケスナックで、隣にかけてきて、いつもとはぐっとトーンを下げて、「これから二人で抜け駆けしませんか?」と、耳打ちしてきた。
私はあのヘンテコなマシンガントークは口説き文句だったのだと、初めて解した。
私が断った直後も後日も、ヘンテコなマシンガントークはひっきりなしに続いた。
R氏によると、K氏は、女性とあらば口説きまくる人物で、真剣に結婚を考えていた本命さんもいたという。
そのK氏がいなくなってしまった、、、、、
新年会の折りにR氏からK氏の訃報を聞かされた時は、余りにあっけない虹渡りだったので、言葉が出なかった。
そして、私の内には、あんなにうざいと感じていたK氏の口説き文句が、他愛もない愛嬌に満ちた語々へと、くるりと反転した。
新年会の後、行きつけの音楽カフェで、R氏と他のSSブログ仲間と弔い酒を交わしたが、今夜は改めて、私一人、家でK氏に献杯したい。
K氏よ!虹の橋の向こうでも、日々、ありとあらゆる女性に あのヘンテコな口説き文句で口説きまくってくれ!!
癌だったという。
今の時代、癌は、必ずしも死に直結する病いではなくなったが、K氏はそれが理由で、虹の橋を渡ることとなってしまった。
私の記憶が間違っていなければ、二年ほど前から「身体の調子が良くない」と、私達とも、一人でも、飲みに行かなくなっていた。
K氏とは、我らがSSブロガーR氏を通じて知り合った人物だった。
逢う度に私に、「レズビアンの人にモテそうな感じー!」とか、「(カラオケで『恨み節』を歌うと)恨み節って感じー!」とか、「(お笑い芸人の)鳥居みゆきに似てるー!」とか、およそ褒め言葉とは縁遠い台詞をひっきりなしに次から次へとふっかけてきていた。
私は正直、よくもまあ、こうもヘンテコな形容ばかりを並べ立てることの出来る うざいおっさんだなあと、煙たく思っていた。
ある時、カラオケスナックで、隣にかけてきて、いつもとはぐっとトーンを下げて、「これから二人で抜け駆けしませんか?」と、耳打ちしてきた。
私はあのヘンテコなマシンガントークは口説き文句だったのだと、初めて解した。
私が断った直後も後日も、ヘンテコなマシンガントークはひっきりなしに続いた。
R氏によると、K氏は、女性とあらば口説きまくる人物で、真剣に結婚を考えていた本命さんもいたという。
そのK氏がいなくなってしまった、、、、、
新年会の折りにR氏からK氏の訃報を聞かされた時は、余りにあっけない虹渡りだったので、言葉が出なかった。
そして、私の内には、あんなにうざいと感じていたK氏の口説き文句が、他愛もない愛嬌に満ちた語々へと、くるりと反転した。
新年会の後、行きつけの音楽カフェで、R氏と他のSSブログ仲間と弔い酒を交わしたが、今夜は改めて、私一人、家でK氏に献杯したい。
K氏よ!虹の橋の向こうでも、日々、ありとあらゆる女性に あのヘンテコな口説き文句で口説きまくってくれ!!
年始のご挨拶 [独り言]
みなさん、あけましておめでとうございやす!
昨年は、あっし・ぼんぼちぼちぼちにとりやして、今まで生きてきた中で一番幸せな年をなりやした。
今年も、今回のブログからOPENさせていただき、この幸せが続く限り続いたらいいな!と思っている次第でやす。
みなさんにも、幸多き2024年となりやすよう!
タグ:年始のご挨拶
年末のご挨拶 [独り言]
みなさん、今年も ぼんぼちぼちぼちブログ「冷たい廊下」に閲覧・コメントくださり、誠にありがとうございやした。
おかげさまで、つつがなく2023年もブログを書き了えることができやした。
みなさんには、感謝の気持ちでいっぱいでやす。
当ブログ、今年は今回をもちやしてcloseさせていただきやす。
みなさん、良いお年をでやす!
タグ:年末のご挨拶
欧米人観光客にウケる意外なツボ [独り言]
先日、中央線快速の下りに座っていたら、国分寺から観光客と思しき欧米人の四人の中年男性が乗ってきた。
と!ドアの上のモニターに、次の駅である「西国分寺」が表示されると、彼ら四人は小さく「OH!」「OH!」と歓喜し、そのうちの一人がスマホで「西国分寺」を撮影し、「やったぜ!」といった表情とポーズをとった。
そして彼らは、その次の国立を過ぎる時も立川が表示された時もチラ見しただけで、無反応だった。
私は瞬間、「何故に西国分寺で???」と、ハテナで頭がいっぱいになった。
だって、西国分寺なんて、単なる東京都下の田舎で、武蔵野線との乗り換えの他、何もない町なのに。
が、今思い返し推測すると、どうやら漢字四文字の駅名というのに、非常に興味を惹かれたのではないかと思う。
欧米人の方々にとって、漢字は図案の様で、とても魅力を覚えると聞く。
彼らはどこまで中央線に乗っていたのか、私は立川で降りたので知る由もなかったが、もしも天狗様を観に高尾まで行くのであれば、その一つ手前に「西八王子」があるので、再び「OH!」「OH!」となって一人がスマホを向けるのだろうな、と思った。
と!ドアの上のモニターに、次の駅である「西国分寺」が表示されると、彼ら四人は小さく「OH!」「OH!」と歓喜し、そのうちの一人がスマホで「西国分寺」を撮影し、「やったぜ!」といった表情とポーズをとった。
そして彼らは、その次の国立を過ぎる時も立川が表示された時もチラ見しただけで、無反応だった。
私は瞬間、「何故に西国分寺で???」と、ハテナで頭がいっぱいになった。
だって、西国分寺なんて、単なる東京都下の田舎で、武蔵野線との乗り換えの他、何もない町なのに。
が、今思い返し推測すると、どうやら漢字四文字の駅名というのに、非常に興味を惹かれたのではないかと思う。
欧米人の方々にとって、漢字は図案の様で、とても魅力を覚えると聞く。
彼らはどこまで中央線に乗っていたのか、私は立川で降りたので知る由もなかったが、もしも天狗様を観に高尾まで行くのであれば、その一つ手前に「西八王子」があるので、再び「OH!」「OH!」となって一人がスマホを向けるのだろうな、と思った。
中野の居酒屋「赤ひょうたん」の素敵な姐さん二人 [独り言]
もう十年以上行きつけにしている中野の大衆居酒屋に「赤ひょうたん」という店がある。
奥の席は複数人で来られたお客さん用で、手前のフロアは、テレビがあって、カウンターで一人でゆったり飲める仕様になっている。
私は一人で行くので、カウンターで瓶ビールを傾けながらコロッケなぞをほおばり、テレビに相づちを打ったり眉をひそめたりして過ごすのだが、カウンターには私の様なお客さんがズラリと並ぶ。
そしていつしか、「あ、今日もいらっしゃる!」というお顔がちらほら浮かび上がり始めた。
その中に、私より遥かに年長の姐さんがおられる。
遠くの席にかけていても、「こんばんは」の一言だけを言うために遠征してくださるのだ。
その謙虚な律儀さが嬉しくて、先に私の方で姐さんを発見すると、「こんばんは」を言いに席を立つようになった。
偶然隣の席になると、ほんの些細な世間話をする。
だが、決して根掘り葉掘り聞いて来ず、私に尋ねた情報は、西荻窪に住んでいる事と苗字だけである。
それ以上は深入りして来ずに、一言二言その時流れているテレビの話しをするだけである。
そして帰り際に、「では又!」と、ハイタッチをして別れるのだ。
又、厨房の姐さんの一人は、料理を運んで来てくださる時、「○○でございます。ごゆっくりどうぞ」と、ここがまるで高級割烹であるかの如き丁寧さと物ごしで仰るのである。
するうち、私の顔も覚えてくださり、他のお客さんに配膳をした後もぐるっと回って来て、「こんばんは、ごゆっくりなさっていかれてくださいね」と、満面の笑顔で会釈してくださるのだ。
私はその姐さんの心遣いも嬉しくて、帰り際には必ず、厨房にいらっしゃる彼女に、「今日も美味しかったです!ごちそうさまでした!」と声を飛ばしてから会計場に向かうのがならいになった。
ごく最近では、姐さんは、「では、明日もお待ちしております」とジョークまで仰る様になられた。
昔、国立に住んでいた時、初めて入った近所のラーメン屋で、いきなり知らないオバサンに、「住んでるのはアパートか一戸建てか?」「一戸建てなら、借りてるのか持ち家か?」「持ち家なら何坪あるのか?」まで、マシンガンの様な勢いで一方的にズケズケと聞かれ、辟易した事があるが、客と客との距離、店員さんと客との距離というのは、私は「赤ひょうたん」くらいが、適切で心地良く感じる。
中野の大人気居酒屋「赤ひょうたん」、人気の理由は、味や安さや大将のひょうひょうとしたお人柄だけではなく、このお二人の姐さんにもあるに違いない!と、近く又、「赤ひょうたん」に行ける予定の日を、指折り数えている。
タグ:中野赤ひょうたん
憧れの苗字 [独り言]
みなさんは、ご自分の苗字、お好きでやすか?
お好きではないかた、好きでも嫌いでもないかた、憧れの苗字ってありやすか?
あっし、ぼんぼちは、二度結婚して二度離婚してるんでやすが、二度とも離婚時に苗字を戻さなかったので、今は人生で三度目の苗字でやす。
元々の苗字と二度目の苗字は、日本人に多い苗字ベスト10の、しかも上位に入る、それはも〜うありきたり中のありきたりな苗字だったので、嫌で仕方がありやせんでやした。
で、今の三度目の苗字は、別段 珍しくも何ともないんでやすが、何とか 多い苗字ベスト10外に抜け出せ、ま〜ぁ、ぼんぼちとしては、妥協出来る範囲に入れ、ようやっと堂々と苗字が言える様になりやした。 苗字で呼ばれるのも嫌ではなくなりやした。
そんなぼんぼちでやすから、苗字に対する憧れというのが、昔から非常に強いわけでやす。
特にダントツ一番に憧れている苗字というのがありやす。
それは、弓削(ゆげ)さん という苗字でやす。
あっしはリアルに、この決して短くはない人生の中で、弓削さんという苗字のかたにお逢いした事も、知り合いの知り合いにいらっしゃった事もないので、かなり珍しい苗字だとお察ししやす。
あっしが弓削さんという苗字に憧れるのは、単に 珍しくて音も字面も美しいというだけでなく、あっしの下の名前とくっつけた時に、リズム的にも良く、そして何より、苗字と名で ちょっと素敵な意味合いが生まれるからでやす。
たぶんあっしは、この先、誰とも結婚しないだろうし、ましてや弓削さんという苗字の男性と巡り合う確率は、宝くじに当たるくらいに低いのは確実なので、「ぼんぼちぼちぼち」の他にどこかでペンネームを使う機会があったら、弓削+あっしの下の名前 を名乗ろうかと目論んでいるほどでやす。
この記事をお読みのかたの中に、もしも弓削さんというかたがいらしたら、一人、優越感にほくそ笑んでくだされ!
憂国忌によせてーーー私の生死観 [独り言]
今年も憂国忌が近づいてきた。
毎年、憂国忌が近づくと、改めて 己れの生死観について考えるわけだがーーー
まあ、この類いの記事は、何年かに一度は、憂国忌前後につづっているわけで、私は、三島由紀夫の自死の理由は、国を憂いてだの大義がどうのなどというのは、彼特有の表向きのカッコつけで、せっかく努力して鍛え上げて誇れるまでになった美しい肉体が老いさらばえてゆくのに耐えられなかった事と、小説を書くテーマも材も尽きてしまった、この二つだと思っているのだけれど、今年も私が本記事で言はむとしているのは、三島の死の理由の真相究明ではない。
あくまで、私が思っている前述の二つな理由にからめた 私自身にもいつかは訪れる死についてのモノローグである。
で、あるから、ここまでお読みいただいて興味がなくなったかたは、読むのをやめてくださって構わないし、「ふん、ぼんぼちの生死観とやらは、どんなもんやろ」と覗いてみたい向きは、読み進んでいただければ幸いである。
私は、三島ほど「幸せな死」を遂げた人間は、稀だと思っている。
人間には誰しも老いは訪れる。
見た目の老いがやって来ない人間なんている筈はなく、小説家でなくとも、やりたい仕事への身体的エネルギーや思考力が無限に持続し続ける人間も、いるわけはない。
人間、人によって順序は様々だろうが、見てくれの老い、体力の老い、思考力の老い は、必ずやってくる。
多くの人間は、「あぁ、若い頃は○○だったのに、こんなになっちまって、、、」と言いながらも、妥協の中に生き続けるわけであるが、そこを妥協せずにスパッ!とカットアウトしたのが、三島である。
私も三島の様な最期を遂げたいと考えている。
否、決して、国家や自衛隊を巻き添えにして大立ち回りを演ずる気はさらさらないが、彼の様に、老いさらばえむとする時期が来たら、スパッ!と逝きたい。
「いやいや、今は人生100年時代だよ」という声がいくつもあがってきそうだが、今の見てくれ、今の体力、今の思考力 が100才まで続くのなら、そりゃ100まで生きていたい。
でも、そんな人間、いるわけがない。
私は、自分が鏡を見て笑顔でいられる、自分の思考したい事を思考出来る、自分が行きたい所へ行ける、それが出来なくなったら、その時が私の寿命だと考えている。
しわくちゃな顔になって腰も曲がり、老人ホームに入って、意味不明の言葉を延々繰り返して、そのうち寝たきりになってただ虚空を見上げてフェイドアウトしてゆくなんて、絶対に嫌!!
三島のお母上は、彼の自死の知らせを聞いて、静かにこう仰ったという。
「あの子は、やりたい事をやり遂げたんです」ーーーと。
毎年、憂国忌が近づくと、改めて 己れの生死観について考えるわけだがーーー
まあ、この類いの記事は、何年かに一度は、憂国忌前後につづっているわけで、私は、三島由紀夫の自死の理由は、国を憂いてだの大義がどうのなどというのは、彼特有の表向きのカッコつけで、せっかく努力して鍛え上げて誇れるまでになった美しい肉体が老いさらばえてゆくのに耐えられなかった事と、小説を書くテーマも材も尽きてしまった、この二つだと思っているのだけれど、今年も私が本記事で言はむとしているのは、三島の死の理由の真相究明ではない。
あくまで、私が思っている前述の二つな理由にからめた 私自身にもいつかは訪れる死についてのモノローグである。
で、あるから、ここまでお読みいただいて興味がなくなったかたは、読むのをやめてくださって構わないし、「ふん、ぼんぼちの生死観とやらは、どんなもんやろ」と覗いてみたい向きは、読み進んでいただければ幸いである。
私は、三島ほど「幸せな死」を遂げた人間は、稀だと思っている。
人間には誰しも老いは訪れる。
見た目の老いがやって来ない人間なんている筈はなく、小説家でなくとも、やりたい仕事への身体的エネルギーや思考力が無限に持続し続ける人間も、いるわけはない。
人間、人によって順序は様々だろうが、見てくれの老い、体力の老い、思考力の老い は、必ずやってくる。
多くの人間は、「あぁ、若い頃は○○だったのに、こんなになっちまって、、、」と言いながらも、妥協の中に生き続けるわけであるが、そこを妥協せずにスパッ!とカットアウトしたのが、三島である。
私も三島の様な最期を遂げたいと考えている。
否、決して、国家や自衛隊を巻き添えにして大立ち回りを演ずる気はさらさらないが、彼の様に、老いさらばえむとする時期が来たら、スパッ!と逝きたい。
「いやいや、今は人生100年時代だよ」という声がいくつもあがってきそうだが、今の見てくれ、今の体力、今の思考力 が100才まで続くのなら、そりゃ100まで生きていたい。
でも、そんな人間、いるわけがない。
私は、自分が鏡を見て笑顔でいられる、自分の思考したい事を思考出来る、自分が行きたい所へ行ける、それが出来なくなったら、その時が私の寿命だと考えている。
しわくちゃな顔になって腰も曲がり、老人ホームに入って、意味不明の言葉を延々繰り返して、そのうち寝たきりになってただ虚空を見上げてフェイドアウトしてゆくなんて、絶対に嫌!!
三島のお母上は、彼の自死の知らせを聞いて、静かにこう仰ったという。
「あの子は、やりたい事をやり遂げたんです」ーーーと。